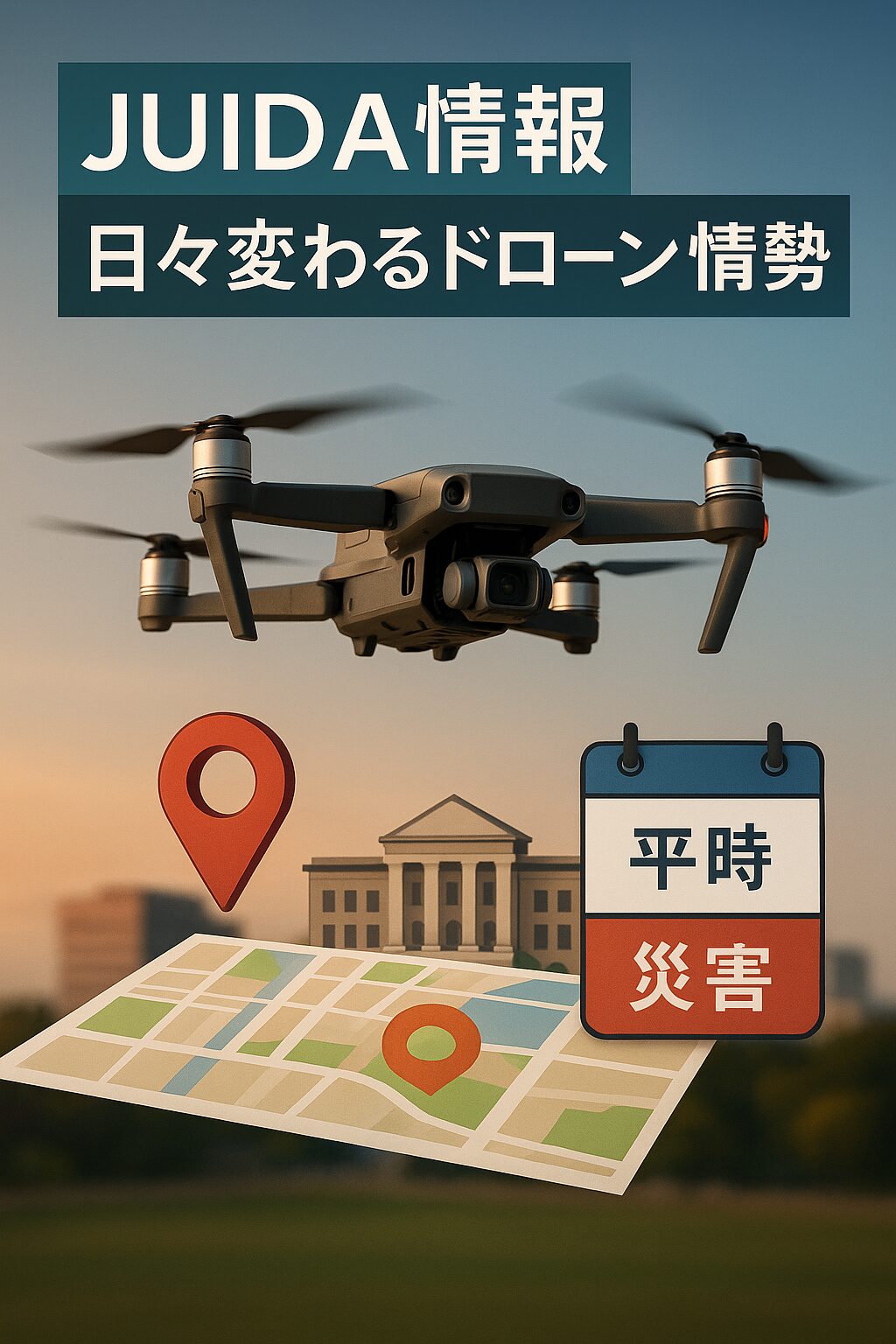ごきげんよう。
「スカイテックラボ」へようこそ。
※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。
【JUIDAニュースレター】の最新情報からのものです。
詳細な情報や最新の更新については、JUIDAの公式サイトをご参照ください。
【JUIDA情報】日々変わるドローンの情勢——全国21市町村と結ぶ「フェーズフリー連携」の意味
今回の大事なポイントは…
JUIDA(日本UAS産業振興協議会)が、全国21市町村で構成される「ささつな自治体協議会」と、災害時だけでなく平時(フェーズフリー)にも連携する協定を締結しました。
対象は情報収集・測量点検・物資運搬・教育・コンサル・調査研究・その他合意した支援まで幅広く、“使うための訓練や仕組みづくり”を平時から進めるという方向性が明確になっています。
本稿はニュース要約にとどめず、「これから始める人」にとって何が変わるのかを、安全・制度・地域活用の3視点で解説します。
なお、違法飛行や危険な運用は決して推奨しません。
各種ルールの最終確認は、必ず一次情報で行ってください。
ニュースの核:フェーズフリーで「備え」と「実装」をつなぐ
フェーズフリーとは、災害時(緊急)だけでなく、平時から準備・教育・検証・運用モデルを回す考え方です。
これにより、操縦や安全手順、データ運用、連絡体制が平時から磨かれ、いざという時に“練度”の差が出ます。
協定の支援領域は次の通りです。
- ① 情報収集(被害状況・インフラ確認・アクセス困難地の俯瞰)。
- ② 測量・点検(橋梁・法面・公共施設などの点検効率化)。
- ③ 物資運搬(安全・適法の条件下での小規模搬送の検証と運用)。
- ④ 教育(操縦・安全・法令・運用体制に関する人材育成)。
- ⑤ コンサル(導入設計・運用設計・ルール整備の支援)。
- ⑥ 調査研究(地域特性に合わせたユースケースの検証)。
- ⑦ その他、協議により必要と認められる活動。
ここから読み取れるのは、「飛ばす」だけではなく「仕組みとして使う」段階に入ったということです。
だからこそ、ルールの理解・安全手順の標準化・住民感情への配慮が、より強く求められます。
対象自治体と広がり:地域単位で学ぶ・備える・使う
協議会に参加するのは、全国21の市町村です。
福島県天栄村、栃木県益子町・高根沢町・塩谷町、石川県志賀町、埼玉県美里町、岐阜県七宗町・白川村、島根県津和野町、福島県棚倉町、佐賀県上峰町、福岡県うきは市、北海道広尾町・苫前町、静岡県松崎町、滋賀県日野町、長野県根羽村・南箕輪村、秋田県美郷町、高知県越知町。
政令市級ではなくても、地形・人口密度・道路網など地域特性に応じた運用を平時から試せることに価値があります。
防災・点検・観光・農林水産など、用途の幅が広いほど、地域の合意形成と説明責任が重要になります。
これから始める人へ——「何を準備すれば良いの?」の地図
ニュースを“自分ごと”にする最短ルートは、安全・制度・コミュニケーションの3点を小さく回すことです。
ここでは、初学者の道しるべとして、注意点と優先順位を示します。
1)安全:現場で“守れる”知識と手順
- 基本ルールの把握:人口集中地区(DID)、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、緊急用務空域などの制限を理解する。
- 特定飛行の判断:夜間・目視外・第三者上空・物件投下・危険物輸送など、該当時は許可・承認または要件充足が必要。
- 安全体制:立入管理・補助者配置・RTH(自動帰還)の確認・機体点検(プロペラ・IMU・コンパス・電池)。
最重要は、“できるだけ安全に”ではなく“安全が確保できないなら飛ばさない”という判断です。
災害・点検の現場ほど、安全に関する説明責任が重くなります。
2)制度:最新情報で迷わない
- 一次情報を確認:運用ルールや申請要否はアップデートされます。
古いブログ記事やSNSの切り抜きで判断しない。 - 地域のルール:自治体管理地・公園・私有地のルール、条例や管理者の許可は空域ルールとは別に存在。
- データの扱い:撮影・測量データの権利、個人情報・プライバシー配慮、第三者映り込みへの対策。
フェーズフリーの運用モデルは、平時から「安全×法令×データ」の三位一体で整えるほど、実装がスムーズです。
3)コミュニケーション:地域と“同じ地図”を持つ
- 目的の共有:何のための飛行か、住民・担当部局・関係者に事前説明。
- 安全の見える化:立入区画・看板・誘導動線・合図、事前告知と当日のアナウンス。
- 記録の管理:飛行計画・ログ・点検記録・ヒヤリハットの記録と振り返り。
地域協定は“合意の器”です。
器を活かすのは、日々のコミュニケーション設計だと理解してください。
初心者が誤解しやすいポイントと回避策
Q1. 「自治体と連携=許可なしで飛ばせる」では?
いいえ。
空域や特定飛行の要件は別問題です。
自治体協定があっても、航空法や関連法令、管理者ルールの順守が前提です。
Q2. 災害時は「安全よりスピード」では?
優先されるのは人命と安全です。
飛行の安全を損なう判断は、結果的に活動全体の遅延・事故・信頼喪失につながります。
飛ばさない判断を含めた運用設計が重要です。
Q3. 「ホビーなら関係ない」?
関係あります。
地域の防災・点検・教育の裾野が広がるほど、安全・法令理解を持った市民パイロットの存在が価値を持ちます。
学びの最初の一歩から、正しい手順に慣れましょう。
編集部の視点:この動きが示す「これから」
今回の協定は、地域単位でドローン運用を“公共サービスの一部”として設計する流れを後押しします。
平時の教育・検証でスキルと体制を底上げし、緊急時の迅速な情報収集・点検・物資搬送へ接続する。
この循環が当たり前になれば、「ドローン=特別な装置」から「社会の基盤ツール」へ進化します。
その要では、住民への説明と安全へのこだわりが欠かせません。
スカイテックラボでは、ニュースの背景や運用の勘所を、初心者にも少しでも迷いが少ない言葉で分かり易い様に解説しています。
そして、制度・技術・現場コミュニケーションの三位一体を、これからも追いかけていきます。
最新情報はXで発信中!
リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!