ごきげんよう。
「スカイテックラボ」へようこそ。
※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。
「ドローンの目視外飛行(BVLOS)」に関する規制が、2025年、米国で大きく変わろうとしています。
ドローンの可能性を広げる鍵であるBVLOS飛行は、従来の航空法や安全基準の壁に阻まれてきましたが、ついに大きな転機が訪れようとしています。
BVLOSは、「目で見えない場所でもドローンを飛ばせる」高度な運用形態です。
物流・災害救助・インフラ点検など、社会インフラの根幹を支える分野での活用が期待されています。
しかし、これまでの規制では、飛行承認のハードルが高く、商用利用が進みにくい状況が続いていました。
今回の記事では、米国連邦航空局(FAA)が2025年に導入を予定しているBVLOS規制「Part 108」の概要を解説するとともに、日本に与える影響や、私自身が考えるドローン業界の今後の展望についてもご紹介します。
「海外の法整備は進んでいるのに、日本はどうなの?」
「規制が緩和されることで、どんなチャンスが広がるの?」
そんな疑問にお応えするために、現地情報・業界の声・JUIDA資格保有者としての視点を交えながら、具体的に解説していきます。
規制が変われば、未来も変わる。
本記事を読むことで、今後ドローンをビジネスに活かすために
「何をすべきか」
「どんな準備が必要か」
が明確になります。
ドローンの目視外飛行(BVLOS)とは?その基本と重要性

BVLOSとは何か?VLOSとの違い
BVLOS(Beyond Visual Line of Sight)とは、操縦者の目で直接確認できない範囲でドローンを飛行させる運用方式です。
これに対し、VLOS(Visual Line of Sight)は操縦者が常に視認できる範囲内での飛行に限定されます。
BVLOSは、飛行エリアや距離に制約がないため、広域での運用や人の立ち入りが困難な場所での業務に最適です。
技術的には高い安全性と高度な操縦支援システムが求められるため、より厳格な法制度と監視体制が必要とされます。
なぜ今「目視外飛行」が注目されているのか?
ドローン業界が大きく飛躍するための鍵が、この「目視外飛行」にあります。
特に物流や災害対応など、緊急性や長距離移動を伴う業務では、BVLOSの活用が現場の効率と即応性を劇的に高めます。
さらに、2022年の改正航空法により、日本でも「レベル4飛行」が制度化されました。
これにより、都市部や有人地帯での目視外飛行が一定の条件下で認められるようになりました。
このような流れの中、各国での制度整備やテクノロジーの進化に伴い、目視外飛行はドローンの本格的な社会実装を進める起点として注目されています。
そのため、操縦者は単なる操作技術だけでなく、制度の理解や安全設計にも精通している必要があります。
BVLOSで可能になる活用事例(物流・災害・インフラ点検など)
BVLOSが実現することで、これまで人が対応していた過酷で広範囲な業務が、より安全かつ効率的に行えるようになります。
たとえば、離島や山間部への医薬品配送、災害発生時の被災地確認、鉄塔・橋梁などの高所インフラの点検などが挙げられます。
物流分野では、ドローンが自律的に商品を運ぶ未来が現実味を帯びてきました。
特に米国では、AmazonやZiplineがBVLOSによる商用配送を先行実施しており、社会的な注目が高まっています。
災害対応では、人命救助に直結する情報収集が迅速に行える点が評価されており、ヘリでは入れないエリアへのアクセスや赤外線カメラによる夜間の捜索など、有人機では難しいタスクに活用されています。
また、インフラ点検においても、ドローンによる遠隔点検で作業の安全性が向上し、業務効率化とコスト削減が実現しています。
従来の高所作業に比べて危険性が大幅に下がるため、建設・電力・通信など多くの業界が導入に積極的です。
米国におけるBVLOS規制の最新動向~2025年「Part 108」の概要~

米連邦航空局(FAA)の新制度「Part 108」とは?
2025年、米国連邦航空局(FAA)は「Part 108」と呼ばれる新たなBVLOS規制の導入を予定しています。
これは、商業ドローンの目視外飛行を一般的に認可することを目的とした新制度であり、ドローン運用の本格的な自由化を意味します。
現行制度ではBVLOS飛行は「例外承認」扱いで、個別申請と安全性の実証が求められていました。
しかし、Part 108では、一定の安全基準を満たした機体・操縦者・運用方法に対し、事前承認なしでも目視外飛行が可能となる方向で制度設計が進んでいます。
この制度は、ドローン業界にとって「商用化フェーズ」への大きな一歩とされ、業界団体・企業・技術者の間で注目度が高まっています。
日本での法改正にも大きな影響を与えると見られており、グローバルに動向を追うことが求められます。
新制度で何が変わる?従来規制との比較
自律飛行の解禁範囲はどう広がるか?
Part 108では、センサーや通信技術を活用した自律飛行が、より広範囲で合法化される可能性があります。
たとえば、飛行中の障害物回避や緊急着陸判断をAIが担うケースなど、従来では申請が複雑だった運用も、基準を満たせば標準的に許可される方向です。
これにより、物流用ドローンのルート飛行や、24時間対応の監視システムが現実的なオプションとなります。
農業や都市インフラなど、長距離かつ反復的な飛行が求められる業務において、飛躍的な効率化が期待されます。
オペレーターの資格要件の変化
現在、米国では「Part 107」に基づく操縦者資格が必須とされていますが、Part 108では、BVLOSに特化した追加資格や訓練が新設される予定です。
これにより、操縦者のレベル向上と安全意識の強化が進むと同時に、業務の専門性が問われるようになります。
日本と異なり、民間主導で訓練機関や教育プログラムが充実している米国では、この資格制度の導入によって、BVLOSを軸にした「新しい職業」が確立されることが予測されています。
日本のBVLOS規制との違いと今後の課題
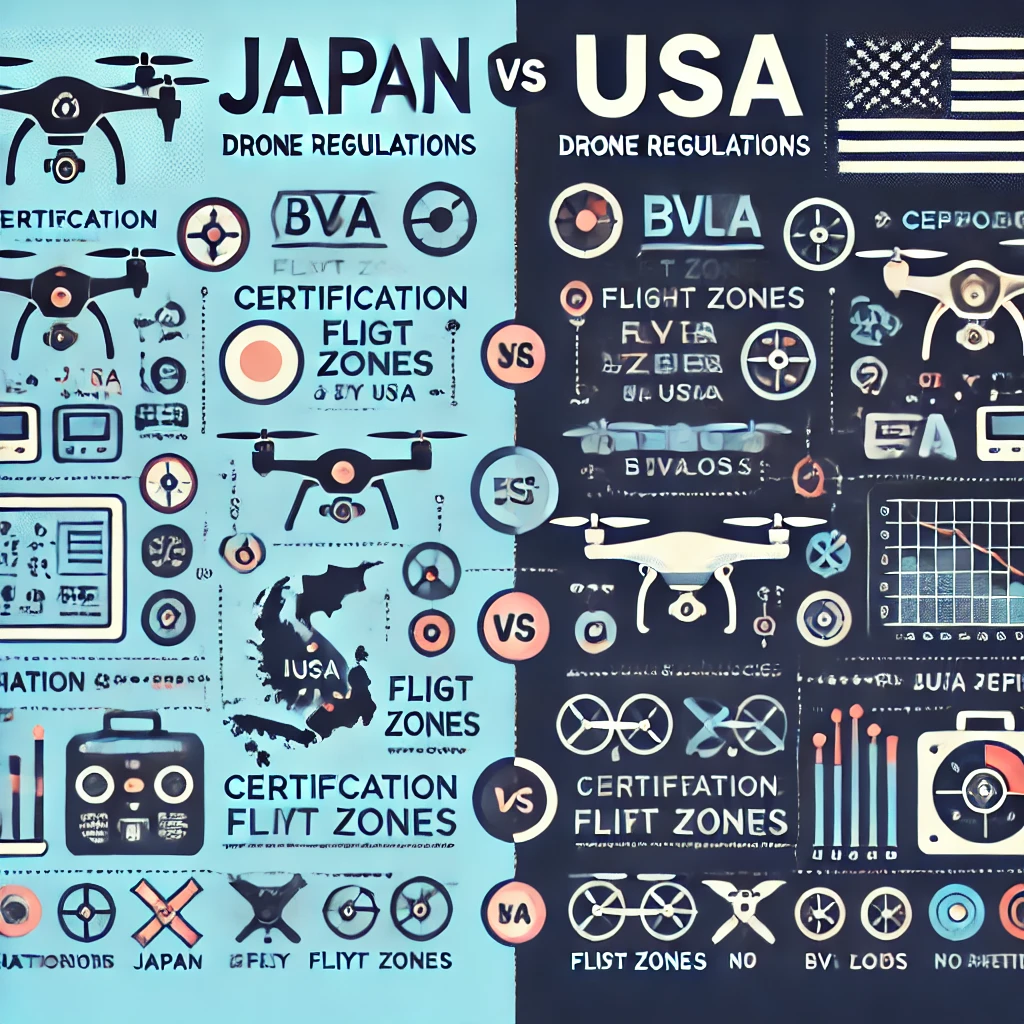
日本のBVLOS制度概要(レベル4飛行など)
日本では、2022年12月に施行された航空法の改正によって、有人地帯での補助者なし目視外飛行、いわゆる「レベル4飛行」が解禁されました。
これは国内のドローン産業にとって、長年の悲願とも言える一歩です。
この制度では、国土交通省が定めた厳格な要件を満たす必要があります。
具体的には、機体認証・操縦ライセンス・運行体制・安全対策の4本柱が求められており、特定の用途・企業に限られた運用が前提となっています。
一方で、日本の制度は依然として「段階的解禁」が基本姿勢であり、フルオート飛行や長距離航行の自由度は限定的です。
これにより、物流・警備・農業などの業務活用を進める上では、制度面の壁が残されているのが現状です。
米国との違いから見える改善点と課題
米国では、2025年に施行予定の新制度「Part 108」によって、一定の基準を満たした事業者に対し、BVLOS飛行を一般的に認める方向へと進んでいます。
これに対して、日本のレベル4制度は「限定的認可」に近く、実用化には高いハードルが存在しています。
制度の柔軟性に加え、米国では民間主導での技術開発と規制提案が積極的に行われているのに対し、日本は行政主導が強く、技術革新と制度改定のスピード感にギャップがある点も見逃せません。
例えば、FAAではすでにリスクベースアプローチにより、飛行エリアや人口密度に応じたリスク評価制度を導入していますが、日本では一律基準での対応が多く、機体や飛行環境に応じた細やかな運用が難しいのが課題です。
今後の国内法改正の可能性と予測
現行の制度が「足がかり」であることは間違いありませんが、次のステージは、事業者ごとの裁量を広げる「運用ベース」への移行です。
すでに2024年には、一部業種を対象に「簡素化されたBVLOS申請手続き」の試行が始まっており、今後さらなる法改正が予想されます。
また、地理空間情報の自動取得や運行管理システム(UTM)の全国展開が進めば、ドローンを都市インフラの一部として機能させる未来も現実味を帯びます。
これに伴い、国や自治体との連携、そして民間企業の技術革新が不可欠です。
将来的には、「BVLOS飛行を前提とした都市設計」や「空の道の整備」など、空のモビリティ革命に向けた制度基盤が形成される可能性もあり、今まさに制度構築の分岐点に立っています。
BVLOS規制が変える産業界の未来

商業ドローン市場の拡大予測と投資トレンド
目視外飛行が当たり前になる社会では、商業用ドローン市場は指数関数的に成長します。
実際、世界のドローン市場は2032年までに6,000億円超に達するという試算もあり、その中心にはBVLOS技術の進展が位置づけられています。
日本でも、物流・警備・点検・測量といった領域に投資が集中しており、スタートアップ企業による革新的な機体開発や運用プラットフォームの構築が急ピッチで進められています。
特に「目視外」を前提にしたビジネスモデルは、既存の市場構造を大きく変えるポテンシャルを持っています。
また、ドローンを活用したスマート農業、港湾物流、空撮広告など、「空から見た生活者ニーズ」に応えるサービスも増加中であり、BVLOS対応が新規参入のボーダーラインとなるケースも珍しくありません。
各業界での活用事例と新たなビジネスチャンス
今後、BVLOS技術は「点の活用」から「面のインフラ」へと進化すると考えられています。
たとえば、医療現場では緊急血液輸送、建設現場では構造物の定期巡回、農業分野では広域の病害監視など、既存の業務を飛躍的に最適化する可能性を秘めています。
これに加えて、自動車や鉄道のインフラと連携したスマートシティ構想も進行しており、ドローンは単なる空撮ツールではなく、「都市の神経網」の一部となる時代が見え始めています。
今後、事業者がどのようにBVLOSを導入するかは、その業界内での競争力やサービスの品質に直結します。
だからこそ、「今から備える」ことが、将来への最大の投資と言えるでしょう。
【比較】JUIDA資格は必要か?BVLOS飛行と資格要件の関係
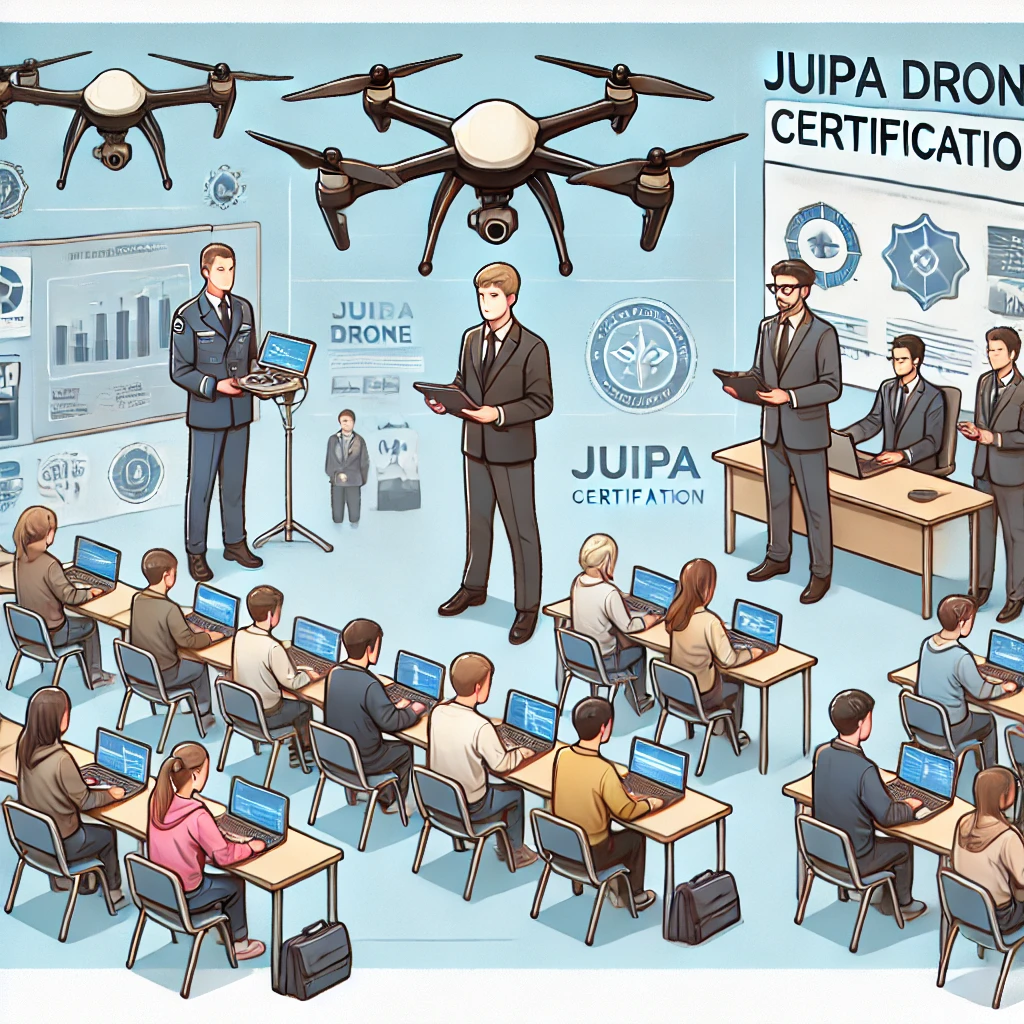
JUIDA資格の役割と取得のメリット
日本におけるドローン操縦者の民間資格として広く認知されているのが、JUIDA(一般社団法人 日本UAS産業振興協議会)による操縦技能証明・安全運航管理者証明です。
これは国が定める国家資格ではないものの、BVLOS(目視外飛行)を行う上での「信頼性の証明」として非常に有効です。
特に、レベル3(無人地帯での補助者なし目視外飛行)やレベル4(有人地帯での目視外飛行)を実施する場合には、事業者や申請先の自治体、警察などへの安心材料として、JUIDA資格保持が強く求められる場面が増えています。
また、JUIDA認定スクールでは、単なる操縦技術だけでなく、法令、安全対策、無線運用、事故事例分析まで体系的に学べるため、独学では身につかない運航リスクへの理解も深まります。
実務的な側面では、保険の優遇や業務委託の際の加点評価にもつながりやすく、今後ますます「標準装備」としての位置付けが強化されるでしょう。
資格が必要な人・必要ない人の線引き
すべてのドローン操縦者がJUIDA資格を取るべきかといえば、そうとは限りません。
たとえば、趣味の空撮や簡易点検など、目視範囲内(VLOS)での飛行を前提とするユーザーには、必須ではありません。
一方で、業務としてBVLOSを行いたい場合や、レベル4飛行に携わりたい方には、取得が実質的に求められる資格です。
特に、企業や自治体との契約が関わる場面では、「無資格者がドローンを飛ばす」という印象を避けるためにも、一定のスキル証明としての資格保持が求められるのが実情です。
逆に、既に他の国家資格(例えば二等無人航空機操縦士)を保有している場合は、内容が一部重複することもあるため、目的や業務の範囲に応じて取得の是非を判断すべきです。
米国との比較で見えるJUIDA資格の今後の可能性
米国においては、連邦航空局(FAA)が発行する「Part 107」ライセンスがBVLOS運用の前提資格となっており、民間資格よりも国家基準での評価体制が確立されています。
これに対し、日本ではまだ制度移行期にあり、JUIDAのような民間資格が現場における信頼性の役割を担っています。
ただし、2022年から段階的にスタートした国家資格制度(二等・一等操縦士)の普及に伴い、今後はJUIDA資格の「補助的」あるいは「入門的」な役割が強まる可能性があります。
とはいえ、教育機関としてのJUIDAスクールの価値や、安全教育への注力は今後も求められるでしょう。
将来的には、国家資格とJUIDA資格が補完関係に位置付けられ、「JUIDAで基礎を学び、国家資格で実務に進む」というキャリアステップがスタンダードになるかもしれません。
【考察】規制緩和が意味するドローンの未来とは

スカイテックマスターKの視点から見る「期待とリスク」
BVLOS規制が緩和されることで、ドローンは一部の特殊業務から、日常生活に溶け込む存在へとシフトしていきます。
物流革命・医療支援・点検インフラの省人化といった「現場ニーズ」が、制度整備によって一気に実現可能となるのです。
しかし、その一方で、急速な導入がもたらす「安全性」への懸念も無視できません。
私自身、スカイテックラボの講習や指導の中で、飛行経験の浅い操縦者が想定外のトラブルに直面するケースを多く見てきました。
制度が整うからこそ、現場では「ヒューマンファクター(人間要因)」への対策が今まで以上に重要になってくると考えます。
また、規制緩和によって「誰でも飛ばせる」環境が整うことは、逆に業界のプロフェッショナリズムを薄めるリスクも内包しています。
その中で、JUIDA資格や国家資格が果たす役割は、単なる知識やスキル以上に、ドローン操縦者としての倫理観や責任感を支える「証明書」として機能していくべきだと考えます。
安全性と自由度のバランスをどう取るか?
ドローンの自由な活用と、社会的な安全の確保。これらは常にトレードオフの関係にあります。
重要なのは、自由と責任のバランスを保つ制度設計であり、制度と運用の両面からアプローチが必要です。
今後、BVLOSが都市部や公共空間でも一般化されれば、騒音・プライバシー・事故リスクといった新たな社会課題も浮上するでしょう。
それに対応するためには、単なる「飛行許可」だけでなく、地域との対話や合意形成が求められます。
ドローンを安全かつ自由に飛ばすには、制度を理解し、運用の実態に合わせて柔軟に対応できる人材の育成が必要です。
まさに、資格制度の強化と同時に、現場レベルでの「教育と実践」が不可欠となる時代です。
まとめ~BVLOSの規制動向を知ることが、未来の一歩に~

今すぐ備えるべき3つのこと
ドローンの目視外飛行(BVLOS)規制の最新動向を正しく把握することは、将来のビジネスと技術革新に向けた準備の第一歩です。
国内外で法整備が急速に進む今、ただ情報を追うだけでは遅れをとってしまいます。
今後の展望を見据え、いま何を学び、何に投資するべきかを明確にすることが求められます。
まず一つ目に大切なのは、「制度理解」です。
米国の「Part 108」のような規制動向はもちろん、日本国内でも制度の変化は頻繁に起きています。
飛行の可否だけでなく、どんな要件が課されるのか、どの資格が必要になるのかまで、制度の深い理解が不可欠です。
次に備えるべきは、「実務スキルの習得」です。
JUIDA資格や国家資格の取得は、単に「飛ばす技術」だけでなく、「リスク管理」や「安全設計」といった、業務レベルでの対応力を鍛える上で非常に有効です。
これからの時代、資格を持たないドローン操縦者は、信頼性の面で選ばれなくなっていくでしょう。
そして三つ目は、「現場との接点を持つこと」です。
制度が整備されても、地域の理解がなければ、BVLOS飛行は進みません。
自治体や企業、教育機関との連携、現場での実証実験の参加など、実務のフィールドに触れる機会を早期に得ることが、結果的に将来の差別化につながります。
法改正にどう対応すべきか?企業・個人の視点から
ドローンの法制度は、もはや「一部の企業だけが対応すればいい」ものではありません。
すべての業界、すべての操縦者に関わるルールとなりつつあります。
それにどう対応していくかは、企業の持続性や個人のキャリア形成にも深く関わります。
企業にとっては、制度変更に合わせた運用ルールの見直し、操縦者の研修体制整備、BVLOS専用機材の導入が不可欠です。
特に、物流・インフラ・農業・警備など「人手不足をドローンで補う」業界では、先行投資が競争優位性に直結します。
遅れれば、顧客からの信頼や安全性の担保を失うリスクも高まります。
一方、個人操縦者にとっては、制度変化に応じた「スキルのアップデート」が重要です。
レベル4対応に必要な国家資格取得を視野に入れるだけでなく、法令知識のアップデート、運航管理技術の習得、無線免許との連携など、横断的な学びが求められます。
さらに重要なのが、「変化を機会として捉える視点」です。
制度改正は煩雑である一方で、新たな市場、新たなビジネスモデルを創出するチャンスでもあります。
現に、ドローン物流や遠隔インフラ点検、医療輸送のような新サービスが、制度の変更と同時に一気に拡大しています。
今後、「BVLOSが当たり前になる時代」が到来したとき、その波に乗れるのは、制度の動きを早くから追い、実践を重ねてきた人と企業だけです。
「ルールが整ったから飛ばす」のではなく、「ルールを見越して準備してきた者」が、次の時代の主役になります。
最新情報はXで発信中!
現場のリアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!



