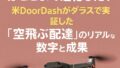ごきげんよう。
「スカイテックラボ」へようこそ。
※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。
【JUIDAニュースレター】の最新情報からのものです。
詳細な情報や最新の更新については、JUIDAの公式サイトをご参照ください。
2025年6月、長崎県が最大100万円の補助金を支給するという非常に注目度の高い制度がスタートしました。
その名も、「ドローンオペレーター育成支援補助金」。この制度は、ドローン人材の確保と地域産業の活性化を目的に、国家資格・民間資格取得にかかる費用の2/3までを支援するものです。
「ドローンの資格を取らせたいけど、コストが高すぎる…」
「助成対象に自社は入るの?今すぐ動くべき?」
そんな疑問を抱える中小企業経営者・人事担当者の方にとって、この補助金はまさに“追い風”となるチャンス。
しかも、この補助金、ただの支援では終わりません。
申請条件・対象経費・申請期限など、制度の中身を正しく理解しなければ採択されないため、正確な情報のキャッチアップが不可欠なのです。
この記事では、長崎県が発表した「ドローンオペレーター育成支援補助金」の最新情報をベースに、以下のような内容をお届けします:
- この補助金で何が支援されるのか?
- 対象となる企業や申請の具体的な条件は?
- 申請に向けて準備すべき資料と注意点
- 過去に補助金を活用した成功事例との比較
ドローン業界を牽引する長崎県のこの制度。
貴社の人材育成戦略にも大きく関わる可能性が高いため、今すぐ内容を把握しておく必要があります。
それでは、令和7年度版の「ドローンオペレーター育成支援補助金」の詳細について、深掘りしていきましょう。
ドローンオペレーター育成支援補助金とは?|制度の概要と背景を徹底解説

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
まず最初に結論から。
この補助金は、長崎県内企業がドローンオペレーター資格を取得する従業員を支援する制度で、国家資格・民間資格の講習費用や試験費用を2/3補助、さらに1社あたり最大100万円まで支給されます。
長崎県が補助金を出す理由と地域活性の狙い
ドローン市場は点検、農業、防災など多岐に広がっており、地方でも高度な業務が可能な人材が求められています。
長崎県はこの需要に応えるべく、地場企業の競争力強化と、都市圏に依存しない産業育成を目指しています。
つまり、この補助金は“地域の雇用と産業を同時に底上げする戦略的投資”なのです。
制度の全体像|対象企業・対象事業・補助率の基本
本制度は以下の要件を満たす企業が対象になります。
(1)従業員に資格取得をさせる費用を負担し、
(2)県が設けるプラットフォームに加入または誓約し、
(3)創業後1年超の県内企業であること。
補助率は国家・民間資格取得費の2/3以内、1人あたりの上限は国家資格で40万円、民間資格で30万円、かつ企業単位で最大100万円まで。
“2/3補助”と“100万円上限”の組み合わせが中小企業にとって現実的な支援水準です。
補助対象となる資格:国家資格と民間資格の違い
国家資格(航空局認定)は法的に認められた操縦スキルの証明となる一方、民間資格(JUIDA等)は実務に直結した訓練内容や就労支援が強み。
国家資格で40万円、民間資格で30万円まで補助される構造は、企業の目的に応じた選択を後押しします。
両方を組み合わせれば最大100万円上限まで活用可能です。
最大100万円の支援額と補助率2/3の意味とは
2/3補助が意味するのは、自己負担が1/3で済むということ。
例えば受講料60万円なら自己負担は20万円と抑えられ、予算計画が立てやすくなります。
中小企業にとっては、採用コストよりも手頃に専門人材を育成できる貴重な機会です。
他制度との違いと「ドローンプラットフォーム」加入条件
国や自治体が実施する他の補助金は、導入機材やイベント開催がメイン。
一方、本制度は“人材育成”に特化しており、ドローン活用を想定した将来の業務基盤作りを狙っています。
また、長崎県が設置する「ドローンプラットフォーム加入または誓約」が申請必須で、これはネットワーキングや講習情報共有の場として機能し、継続的な育成支援のネットを作るための布石です。
JUIDA資格との関係性と活用の可能性
JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)はドローン業界の一定水準を担保する団体です。
民間資格の多くはJUIDA認定講習機関が提供しており、実務的な飛行技術や安全管理ノウハウが身につきやすい設計になっています。
制度を通じてJUIDA資格を取得すれば、即戦力となる人材の確保が可能ですし、その後の業務展開にも強みを得られます。
補助金の申請方法と通過のコツ|必要書類・スケジュール・注意点

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
申請の流れをわかりやすく解説【ステップ形式】
「制度は魅力的でも、申請が煩雑そうで踏み出せない」
そんな声を多く聞きます。
しかし、長崎県のドローンオペレーター育成支援補助金は、ステップをきちんと踏めば通過率が高いと言われています。
必要なのは、要点を押さえた準備とスケジュール管理だけです。
まず申請者は、公式サイトから交付申請書と事業計画書をダウンロードし、自社のドローン人材育成の目的や方法、対象資格の選定理由を明文化します。
ここでは、単なる資格取得の羅列ではなく、「なぜこの講習でなければならないのか?」を説明するロジックが重要になります。
交付申請書・事業計画書の書き方ポイント
申請で最も重視されるのが、「継続性」「実効性」「波及効果」です。
たとえば、「資格取得後の業務内容」「地域課題の解決」など、具体的なビジョンを明記すると、審査側の納得感を高められます。
単なる社内研修ではなく、社会的な意義を絡めたストーリー性が評価を左右するという点を意識しましょう。
誓約書・税証明書など書類の準備と注意点
申請に必要な添付書類は多岐にわたりますが、「書類不備」は不採択理由の最たる要因です。
法人税・県税・消費税の未納がない証明書、ドローンプラットフォームへの加入確認書類、そして誓約書など、公的な文書はすべて「発行6ヶ月以内」の原本が必要です。
手配に時間がかかるため、申請の1ヶ月以上前から準備を始めるのが理想です。
申請スケジュールと「間に合うためにすべきこと」
今回の補助金は、令和7年7月18日が申請締切(当日消印有効)となっています。
実際に書類を揃えてからでは間に合わない可能性が高いため、「逆算スケジュール」で計画を立てる必要があります。
特に注意すべきは、受講講座の内容・費用が分かる資料の入手です。
対象となるドローンスクールに確認し、講座名、受講期間、費用明細などを明記した資料を確保しておきましょう。
これが無いと、補助対象経費として認められません。
不採択を避けるコツ|よくある失敗と対策
補助金申請において、「不採択の8割は事前準備不足に起因する」とも言われています。
特に多いのは、以下の3つの落とし穴です。
一つ目は、「事業内容と補助制度の目的が一致していない」こと。
制度が求めるのは「ドローンによる産業振興と雇用の創出」であり、社内の人材育成で終わっていては評価されません。
申請理由に社会性を含めることがカギです。
二つ目は、「金額根拠の説明があいまい」な点。
受講費や受験料が具体的に示されていないと、不透明な印象を与えます。
講座実施機関からの正式見積もりを添付しましょう。
三つ目は、「記載内容に一貫性がない」こと。
申請書・計画書・証明書類で記載内容が異なると、信頼性が大きく損なわれます。
最終確認は第三者にチェックしてもらうのが無難です。
他の補助金との併用は可能か?制度の注意事項
補助金制度には多くの種類がありますが、「国・県・市町などの他制度と併用することはできません」。
本制度の公式文書にも明記されており、他の公的助成制度から同様の目的で支援を受けていると、交付対象外となります。
また、申請時点で補助対象となる講習の実施・契約が済んでいる場合も不適格です。
「交付決定前に発注・受講・支払が完了しているとNG」となるため、申請受理後に動くことが絶対条件です。
「先に動いておけば良かった…」という声は少なくありません。
この補助金に限らず、補助金は“採択されてから動く”が基本です。
この補助金で企業が得られる3つの成果|成功事例と今後の展望

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
ドローン人材育成で得られる経営メリット
コスト削減だけではない、採用・人材戦略の変化
ドローンオペレーター育成支援補助金を活用する最大の成果は、「社内人材の戦力化」にあります。
特に、これまで外注に頼らざるを得なかった測量・点検業務を、社内の従業員が担えるようになることは、継続的な経費削減に直結します。
外注1回あたり数十万円に及ぶ調査や撮影が、内製化により実質0円に近づく。
単なる費用削減に留まらず、教育投資という観点からも高い効果をもたらします。
さらに注目すべきは、採用・人事戦略への波及効果です。
特定の技能を持つ人材を「社内で育てられる」環境は、若手や中堅層のモチベーション向上に直結します。
特に地方企業では、「キャリアの見通しが描ける職場」があることは、定着率を左右する大きなファクターです。
補助金制度を通じて教育体制が整えば、企業の魅力そのものが高まります。
地域密着型サービス・測量・点検事業への応用
近年、地方におけるドローンサービスの需要は急拡大しています。
老朽インフラの点検、農地管理、防災対策、さらには観光プロモーションなど、用途は多岐にわたります。
その中でも、専門性の高い操作が求められる分野において、自社内でライセンスを持つスタッフを確保できることは、業務のスピードと柔軟性を大きく変えます。
例えば、ドローンによる屋根点検を例に取ると、外注業者に依頼すれば3〜5日かかる工程が、社内対応なら即日完了。
この“即応性”は、クライアント満足度とリピート率の向上に大きく寄与します。
しかも、補助金を活用すれば、導入リスクを最小限に抑えて人材を育成できる。
まさに、地域密着型ビジネスの武器と言えるでしょう。
成功事例に学ぶ!補助金を活用した企業の変化
すでにこの制度を活用した企業では、業務効率と社員スキルの“両輪”が向上したという報告が相次いでいます。
長崎県内で建築設計を手がけるA社では、資格を取得した若手社員をドローン担当にアサイン。
測量業務をすべて社内で完結させることで、年間の外注費を60万円以上削減できたといいます。
また、動画制作会社のB社では、JUIDA認定資格を取得したスタッフが空撮サービスを新たに立ち上げ、その売上が半年で200万円を突破。
補助金がなければ手を出せなかった新規事業を、低リスクで試すことができたことが決め手だったそうです。
このように、育成=コストという固定観念を打ち破った企業が、着実に成果を出しているのです。
今後のドローン市場と長崎県が目指す未来像
長崎県がこの制度を推進する背景には、「地域課題をドローンで解決したい」という明確な意図があります。
たとえば、高齢化が進む中山間地では、人手不足による農業の機械化ニーズが急速に高まっており、農薬散布や生育管理をドローンで行う実証事業もすでに始まっています。
さらに、インフラ点検や災害時の情報収集など、行政との連携領域も増加。
今後は、民間事業者と自治体が共同で運用する「地域ドローンプラットフォーム」の構築も視野に入っており、この制度を活用した人材が、その中心に立つ未来が想定されます。
つまり、今回の補助金は単なるコスト支援ではなく、将来の地域戦略の中核を担う“基礎投資”なのです。
この制度を使うべき企業の特徴と今すぐやるべきこと
「補助金を使うべきか?」ではなく、「使わない理由がない」。
それが今の結論です。
特に、以下のような企業には制度活用を強く推奨します。
・既存事業にドローン技術を取り入れたいが、初期コストが障壁になっている企業
・若手人材にスキルとキャリアの両面で価値を提供したい中小企業
・今後、自治体との連携や公共事業を視野に入れている事業者
また、申請締切(2025年7月18日)までに間に合わせるには、今すぐ準備を開始する必要があります。
講座内容の確認、書類取得、社内での事業計画の精査
──その一つひとつが採択の鍵を握ります。
本制度は、ドローンという成長産業の「入り口」として、非常に実用的な支援です。
単に「もらえるお金」ではなく、「企業成長の起爆剤」として、ぜひ積極的に検討していただきたい内容です。
最新情報はXで発信中!
リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!