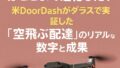ごきげんよう。
「スカイテックラボ」へようこそ。
※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。
「ドローンで農業の未来が変わる」──そんな予感が現実味を帯びてきました。
2025年6月、JA全農・KDDI・KDDIスマートドローンの三者が、「スマートドローンと自律飛行型ドローンを活用した事業検討」に関する基本合意書を締結しました。

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
この記事では、この協業がどのように日本の農業を変革していくのか、背景にある課題と共に、ドローン活用の新たなフェーズを深掘りしていきます。
「水稲の遠隔防除」というテーマからスタートした実証は、やがて果樹や畑作へも波及し、複数ドローンを遠隔一括制御するシステムにまで発展する見込みです。
KDDIは上空の通信インフラ(4G LTE)を、JA全農は農家とのネットワークと現場の知見を提供し、「省力化×再現性×データ化」という農業の三大課題に真正面からアプローチ。
この連携の鍵は、“ただのドローン活用”ではなく、農業×通信×自律飛行の融合です。
記事内では、ドローン国家資格保有者としての私「スカイテックマスターK」が、現場の視点からこのニュースをどう読み解くか、農業従事者にとって本当に意味があるのか?といった視点で独自考察を交えて解説していきます。
さらに、公式発表の内容をもとに、2027年の事業化に向けたロードマップや、今後予想される法規制や実運用の課題についても取り上げます。
スマート農業に本気で関心がある方や、ドローンをビジネスで活用したい方にとっては、見逃せない内容となっています。
スマートドローンと自律飛行型ドローンとは?|基本概念と最新トレンド

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
スマートドローンとは何か?従来型との違い
スマートドローンとは、高度なセンサー・AI・通信機能を搭載した次世代型ドローンを指します。
従来のドローンが主に人間の操縦によって飛行していたのに対し、スマートドローンは飛行経路の自動設定や障害物の自動回避、リアルタイム通信による状況把握などが可能です。
特に注目されているのが、KDDIスマートドローンのようにLTEやStarlinkなどの通信網と連携することで、遠隔地からの長距離・高精度な運用が実現できる点です。
これにより、これまでアクセスが困難だった山間部や農村地帯でも、安定した業務運用が可能になります。
また、スマートドローンにはAI解析によるデータ処理機能が内蔵されていることが多く、飛行後の処理ではなく“飛行中の分析”が可能な点も革新的です。
たとえば、作物の育成状態や病害虫の有無を即座に判断し、その場で対応を取れる仕組みは、農業分野で特に有効です。
自律飛行型ドローンの特徴と進化ポイント
自律飛行型ドローンとは、事前に設定されたルートや条件に従って、人の操作を必要とせずに飛行・作業を行うドローンです。
スマートドローンとの違いは、通信機能や外部連携の有無というよりも、完全な自動化・運用レベルに焦点がある点にあります。
たとえば、KDDIスマートドローンでは、1人のオペレーターが複数機体を管理する遠隔運航が検討されており、これは従来では考えられなかった効率性です。
さらに、自動充電ポートを備えたモデルでは、作業後の帰還・充電・再飛行までもが一連のルーチンとして組み込まれています。
現在では、3Dマッピング・気象センサー・AIによる経路最適化などが標準化されつつあり、人が介入しなくても安全・正確な作業をこなすレベルにまで達してきています。
この技術革新が、農業・土木・物流など幅広い分野でのドローン活用を後押ししています。
農業分野でのドローン導入が進む背景
少子高齢化による担い手不足の現状
日本の農業は今、深刻な労働力不足に直面しています。
農林水産省の資料によれば、農業従事者数は2022年時点で約116万人ですが、これが2045年には約3分の1の30万人程度まで減少するとの予測があります。
特に60歳以上の従事者が7割以上を占める現状では、今後の持続可能な営農体制はもはや不可能と言っても過言ではありません。
そこで期待されているのが、労働集約型から技術集約型へのシフトです。
ドローン技術はまさにその中心にあり、人手を大きく削減しつつ、作業品質を維持・向上させるための鍵とされています。
農作業の省力化・自動化が求められる理由
田畑の広大化、天候変化への即応、病害虫の早期対応など、現代の農業にはかつてないスピードと精度が求められています。
こうした中、スマートドローンと自律飛行型ドローンが提供する自動化ソリューションは非常に魅力的な存在です。
たとえば、水稲に対する農薬の自動散布では、人が散布するよりも3倍速いスピードで実施可能とされ、身体的負担や熱中症リスクを大幅に削減できます。
さらに、均一な散布と飛行ログの記録により、トラブル時の追跡性や施策の改善にも役立ちます。
これに加え、飛行許可・電波確保・メンテナンスなどを一括で支援する体制が整えば、農業者は専門的な知識がなくても安心して導入できます。
KDDIとJA全農が取り組む構想は、まさにこのような「全自動・ワンストップ型の農業支援」に繋がっていくのです。
これらの背景をふまえ、今後「スマート農業」は農業経営者にとってコスト削減と効率化、そしてデータ活用による意思決定の強化という3つの恩恵をもたらすものとなっていくでしょう。
どこが“スマート農業”なのか?|自律飛行型ドローンがもたらす革新

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
水稲対象の遠隔防除サービスの中身
2025年度から開始されるJA全農とKDDIによる実証実験は、水稲を対象とした遠隔防除サービスに焦点を当てています。
これは、スマートドローンを活用して、圃場(ほじょう)に直接人が入ることなく、農薬の散布を実施するという取り組みです。
従来は人が防除作業を行うため、体力的にも労力的にも大きな負担がかかっていましたが、自律飛行型ドローンを用いることで、この問題を根本的に解決する狙いがあります。
特筆すべきは、遠隔での一括操作によって複数の圃場に対応できる点。
これまで散布に要していた時間を最大70%削減できると見込まれており、効率性と安全性の両立が実現可能となります。
特に、夏場の高温下での作業を避けられる点は、作業者の健康リスク軽減にもつながるでしょう。
複数ドローンの同時制御の仕組み
今回のプロジェクトの中核技術の一つが、複数のドローンを1人のオペレーターが同時に制御する仕組みです。
この方式は、KDDIスマートドローンが開発を進める「遠隔運航管理システム」によって支えられています。
これまでは1人が1機体を操作する必要がありましたが、このシステムを導入すれば、熟練者1名で最大3~5機を同時に運用できるようになります。
監視カメラや飛行ログ、飛行前後の点検フローも自動化されており、属人性の排除と高い再現性を担保できるのが大きな強みです。
さらに、KDDIはLTE通信や衛星通信(Starlink)との連携を想定しており、電波が届きにくい山間地や離島などでも安定した遠隔操作が可能です。
これにより、地方や人手不足の地域でもスマート農業の導入が現実のものとなりつつあります。
AI・センシング・データ連携の今後
測量・診断・3Dマップの活用シナリオ
AIとセンシング技術の進化により、ドローンは単なる空撮機器から、農地の「情報収集装置」へと変貌しています。
今後の展望として、農地の測量や病害虫の発生エリア診断、収穫予測といった分野での応用が急速に進むと見られています。
中でも注目すべきは、3Dマップと連動した自動飛行ルート設定。
これにより、作物の高さや地形に応じた飛行計画をAIが最適化し、より精密な農作業の実施が可能となります。
また、同時に蓄積されるデータは、今後の施肥設計や収穫タイミングの判断材料として活用され、経験則からデータ駆動型農業への転換が進むことが期待されています。
自動充電ポート付きドローンの可能性
KDDIスマートドローンが開発する自動充電ドローンにも注目です。
これは、定められたタスクを終えると自動で帰還し、ポートでの充電を行ったうえで再出動するという仕組みです。
人の手を借りることなく、連続的に飛行作業を実施できるこの技術は、ドローン活用の“常時運用化”に大きく貢献します。
さらに、充電ステーションとAIスケジューラーを組み合わせれば、最適なタイミングでの飛行・充電・点検を完全自動で実行する未来もすぐそこまで来ています。
これにより、農業従事者が本来の経営判断や戦略に時間を割ける環境が整っていくでしょう。
他社の事例と比較して見えること|ドローン活用の成功パターン

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
楽天×ドローン物流の地域モデル
楽天グループはすでにドローン物流の実証実験を複数展開しており、山間部や過疎地域において生活必需品や医薬品の配送で実用的な成果を挙げています。
このモデルの強みは、物流網が整っていない地域へのアプローチと、ラストワンマイル配送の自動化にあります。
農業分野とは目的が異なるものの、無人・遠隔操作・AIルート最適化という技術基盤は共通しており、ドローン活用の汎用性を証明する好例です。
特に自治体との連携体制や、地域住民との合意形成プロセスは、KDDIとJA全農のスマート農業モデルにも活かされるべき視点です。
DJIの農業用ドローンとKDDIの違い
DJI社の農業用ドローンは、世界中のユーザーに広く導入されており、散布精度の高さ・安定した飛行性能・導入コストの安さが評価されています。
特に「T30」や「Mavic 3 Multispectral」などのモデルは、日本でも導入が進んでいます。
一方で、KDDIのスマートドローン事業は、通信・遠隔運航・データ連携という観点において包括的な農業支援を構築しているのが特徴です。
DJIが高性能な機体そのものを提供するのに対し、KDDIは運用体制の構築支援・ライセンス教育・インフラ整備まで一体的に設計しており、提供価値のスケールが異なります。
つまり、機体の性能面ではDJIが先行していますが、日本の農業の現場課題に合わせて制度設計されたのがKDDIモデルとも言えるでしょう。
他国(米・中)のスマート農業との比較
アメリカでは、John Deereなどの農機メーカーがAI搭載のトラクターや収穫機と連携するドローン技術を進化させており、精密農業(Precision Agriculture)という概念が浸透しています。
作物別の生育分析からピンポイント施肥まで、徹底したデータ活用による生産効率化が進行中です。
中国ではDJIが農業用ドローン市場のリーダーとして強く、国家主導の政策支援によって急速な導入が進んでいます。
これにより、単なる技術導入に留まらず、農村インフラの近代化も実現しつつあります。
こうした海外事例と比較すると、日本では導入スピードこそ遅れていますが、「地域特化・現場密着・制度対応型のスマート農業」として進化する余地が大いに残されていると言えます。
筆者の考察|ドローン農業は誰のための技術なのか?

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
現場視点で見る「導入すべきか」の判断基準
現場での導入判断において、機体の性能や価格だけを見て選ぶのは危険です。
むしろ大事なのは、そのドローンが現場の人手・圃場環境・作業サイクルに適応するかという視点です。
私はJUIDA資格を取得後、多くの現場で農業用ドローンの導入相談を受けてきましたが、操作できても活用できていない例が少なくありません。
KDDIのように運用全体をカバーする構成であれば、“人材・設備・申請”の3点をセットでカバーできる点が重要です。
JUIDA有資格者から見た現場とのギャップ
JUIDAの教育プログラムは安全飛行や法律知識を網羅していますが、農業での実務に即したカリキュラムが少ないのも事実です。
たとえば、GPS障害時の対応やバッテリー管理、気象リスク回避など、現場では想定外のことが頻繁に起こります。
ドローンを「農機」として使うには、単なる操縦スキルを超えた“総合運用能力”が求められます。
この点において、KDDIスマートドローンアカデミーのような現場直結型教育の充実が、今後の成否を分けるカギになるでしょう。
テクノロジー依存で失われるものとは?
最後に触れておきたいのは、テクノロジーが万能ではないという視点です。
ドローンの導入が進むほど、農作業は効率化されますが、その一方で、地域との関わり・季節感・作物への直感といった“感覚的な営農の知”が失われる懸念もあります。
すべてを自動化することが最適解なのか──これは導入を検討するすべての農業者が考えるべきテーマです。
ドローンはあくまで「支援ツール」であり、主役は現場で汗を流す農家自身。
この原点を忘れず、使い方を誤らないことが、スマート農業を成功させる唯一の道なのです。
まとめ|基本合意書から始まるスマート農業の未来と次の一手
3者の協業がもたらす具体的な恩恵とは?
今回の基本合意書によって明らかになったのは、JA全農・KDDI・KDDIスマートドローンの三者連携が、スマート農業の加速装置となるという事実です。
各社が持つ資源──JA全農は農家ネットワーク、KDDIはインフラと通信技術、KDDIスマートドローンは運航管理と現場展開力──を融合することで、農業現場の省力化・効率化・標準化が進みます。
特に水稲を対象とした遠隔防除サービスのように、ドローンで自律的に作業をこなしながら、リアルタイムでデータを蓄積・解析するモデルは、これまでの営農スタイルを一新する可能性を秘めています。
また、作業ログや飛行記録を共有できる体制が整えば、農協側の監査や補助金申請にも活用でき、実務上の煩雑さも大幅に軽減されます。
今後のステップと読者ができること
KDDIとJA全農の発表では、2025年度中に水稲対象の遠隔防除実証を進め、2027年度には商用展開の開始を目指すとされています。
その過程では、各地域における通信環境の整備、操縦者育成、自治体・関係機関との連携強化が欠かせません。
読者の皆さんが今できることとしては、まずスマートドローンに関する基礎知識と制度動向の把握が第一歩です。
JUIDA資格の取得や、KDDIスマートドローンアカデミーの受講など、将来のスマート農業担い手としての準備を始めておくことが、いずれ大きな武器となります。
加えて、自身の農地や業務において、どの作業がドローンに置き換え可能かを検討する視点も必要です。
一部だけでも導入することで、実感ベースでの業務改善が得られ、その成功体験が導入推進の原動力になります。
スマートドローン導入の判断材料まとめ
スマートドローンと自律飛行型ドローンを活用した事業検討において、導入を検討する際に重視すべき視点は大きく3つあります。
まず1つは、作業の“置き換え”だけで終わらせないこと。
ドローン導入はあくまで手段であり、収量向上・品質安定・記録整備といった最終目的に直結させる必要があります。
2つ目は、導入コストと運用リソースのバランス。
いくら高性能な機体であっても、オペレーションの負担が増えては本末転倒です。
だからこそ、KDDIが推進するような「一括支援・教育・通信環境のパッケージ提供」は、現場視点で非常に有効です。
最後に、地域全体での導入・活用のビジョンが描けるかが重要です。
個々の農家で完結するのではなく、農協・自治体・民間企業が連携して運用するモデルこそ、持続可能なスマート農業の未来を築くカギとなります。
「スマートドローンと自律飛行型ドローンを活用した事業検討」という枠組みは、農業従事者だけでなく、技術者・政策担当者・地域住民すべてに関わるトピックです。
今後、どのように制度が整備され、現場に実装されていくか──そのプロセスを継続的に追いかけ、“現場で使える知識”として発信していくのが、当ブログ「スカイテックラボ」の使命でもあります。
【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
最新情報はXで発信中!
リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!