ごきげんよう。
「スカイテックラボ」へようこそ。
※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。
「Terra Droneってよく聞くけど、結局どんな会社?」
「Uniflyって何がすごいの?」
──そんな疑問を持っているあなたに、今まさに押さえておくべきニュースを、ドローン専門ブロガーの視点から噛み砕いてお届けします。
Terra Drone株式会社が展開する海外戦略の中核として注目されているのが、ベルギーの子会社 Unifly の動きです。
2025年4月、このUniflyが欧州の次世代空域管理プロジェクト「ENSURE」に正式参画したことで、ドローン業界に新たな衝撃が走りました。
このプロジェクトの肝は
「ドローンと有人航空機が共存できる空域の実現」
にあります。
空の交通ルールが見直されようとしている今、Terra Droneが“主導”する意味とは何なのでしょうか?
本記事では、
- なぜTerra DroneがUniflyを欧州の中枢プロジェクトに送り込んだのか
- ENSUREとは何か?U-SpaceとATM統合の背景とは
- この動きが日本やJUIDA民間ライセンスにどう波及するのか
といった観点から、ただのニュース解説に終わらない“掘り下げ”をお届けします。
私自身、2020年からドローン業界に入り、国内外の運航管理システム(UTM)に関心を持ってきました。
Uniflyが提唱するリアルタイム空域調整「DAR」の技術革新は、間違いなく今後の空の在り方を変えると感じています。
未来の空のインフラがどう変わるのか?
その最前線を一緒に覗いてみましょう。
【注目の背景】Terra DroneとUniflyが動き出した理由
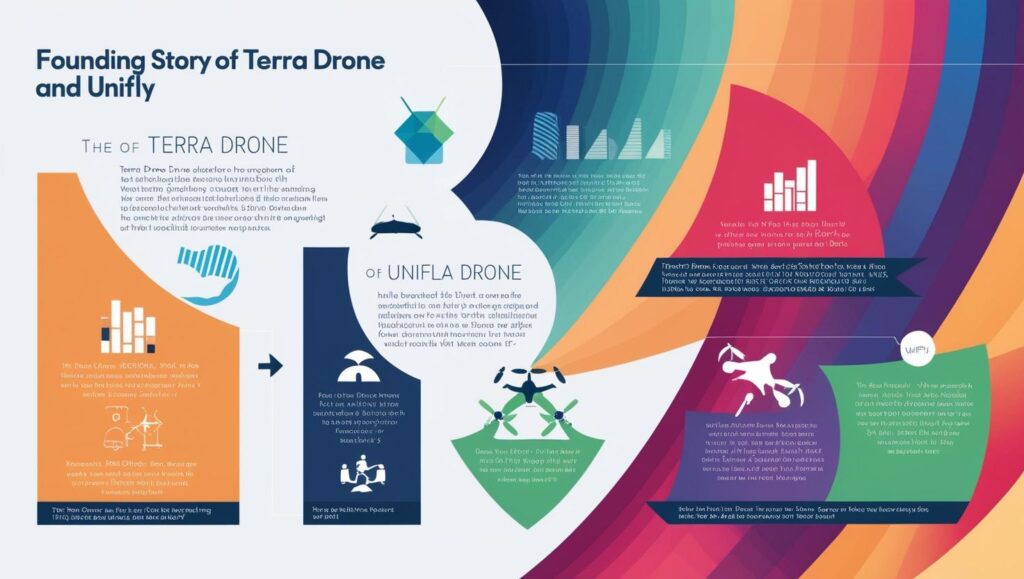
ドローン市場の急拡大と欧州の空域管理の課題
世界のドローン市場は年々拡大し、2030年には約9兆円規模に達するといわれています。
特に商業用途──測量・物流・インフラ点検などの分野での利用が進み、無人航空機の空域活用が社会課題の解決に直結する時代に突入しています。
その一方で、無人航空機と有人航空機が同じ空を共有するという新たな課題も生まれました。
従来の航空交通管理(ATM)では対応しきれないレベルの細かな空域調整が求められ
「どう安全に共存させるか」
が欧州を中心に議論されています。
そこで欧州連合が進めるのが
「U-Space」という概念です。
これはドローン向けの空域運用ルールを整備し、既存の航空システムと統合して運用効率と安全性を高める取り組みであり、今後のグローバルスタンダードにもなり得る枠組みです。
Terra DroneがUniflyを子会社化した戦略的背景
Terra Droneは、ドローンの運航支援や測量サービスを提供する日本発のグローバル企業です。
注目すべきは、空飛ぶクルマや高密度エリアのUTM(無人航空機運航管理)領域への先行投資を続けている点。
2016年にベルギーのUnifly NVと提携し、2023年には51%の株式を取得。
子会社化によって、欧州の先進的な空域管理プロジェクトに本格参画できる体制を整えました。
Uniflyは、すでに欧米8カ国で国家レベルのUTMシステムを提供しており、欧州航空インフラのデジタル化を牽引する存在です。
この戦略的パートナーシップにより、Terra Droneは単なるドローンサービス企業から、“低空域の交通管理”をグローバルにリードする企業へとポジションを変えていきました。
なぜ今「ENSURE」プロジェクトが重要なのか?
2025年4月、Uniflyは欧州の航空管制近代化プログラム「SESAR」のプロジェクトの一つ、「ENSURE」への正式参画を発表しました。
この動きは、空域のデジタル変革を本格化させる号砲とも言えるもので、ドローン運用と航空交通の完全統合に向けたステップです。
ENSUREは「U-Space」と「ATM」をつなぐ共通インターフェースの開発を目的としており、リアルタイムの空域調整(DAR)や、航空管制官とドローンオペレーターの連携強化を実現します。
従来、空域の調整には数時間~半日かかっていたプロセスが、デジタルツイン+リアルタイム通信によって数分単位に短縮される見込みです。
これにより、緊急物資の空輸や都市内ドローン物流など、時間との戦いが求められるミッションでも、安全かつスムーズな飛行が可能になります。
こうした流れの中で、Terra DroneがUniflyを通じて参加する意義は極めて大きいといえます。
なぜなら、このシステムが標準化されれば、日本にも波及し、国内ドローン運用の常識が一変する可能性があるからです。
【プロジェクト解説】ENSUREとは何か?その全貌を探る
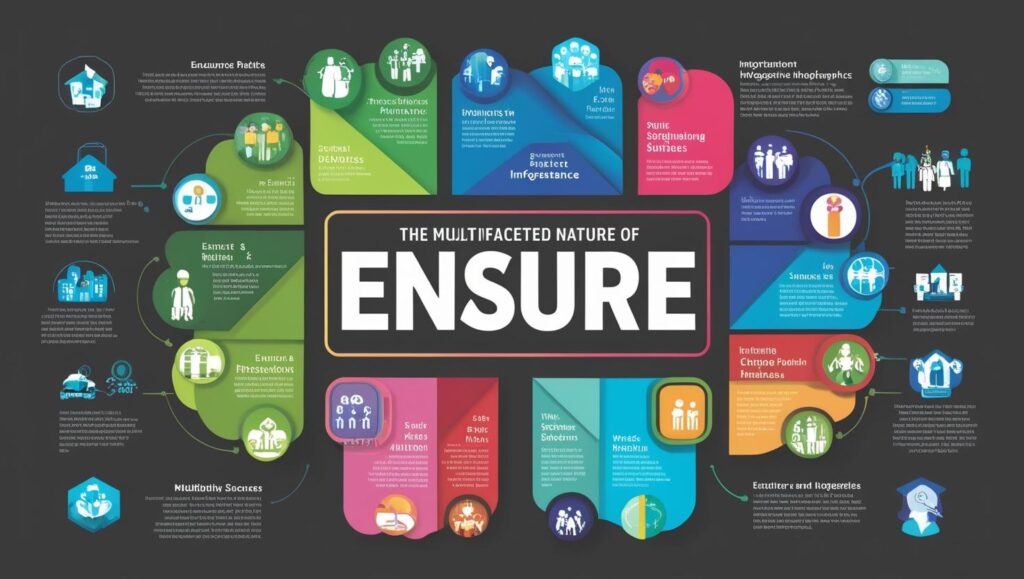
U-SpaceとATMの統合とは何を意味するのか
ドローンと有人機が同じ空域を飛ぶ未来を実現するためには、U-Space(ユー・スペース)と呼ばれる無人航空機専用の空域管理概念と、従来の有人航空機向け航空管制システム(ATM=Air Traffic Management)とのシームレスな連携が不可欠です。
U-Spaceは、欧州航空安全庁(EASA)が主導する無人航空機専用の運用枠組みで、ドローンが都市部や高密度空域で安全に飛行できる環境を構築します。
一方ATMは、航空機の飛行ルートや高度をリアルタイムで調整・監視する伝統的なシステムです。
この2つのシステムが統合されることで、空域のデジタル化が一気に進み、従来では考えられなかったスピードと精度で空域の調整が可能となります。
ENSUREプロジェクトにおけるUniflyの役割と貢献
ENSURE(ENabling Seamless U-space integRation in Europe)プロジェクトは、SESAR 3 Joint Undertakingが中心となり進めている、次世代の空域管理を現実のものにする共同研究です。
Uniflyは、このプロジェクトにおいて、U-SpaceとATMのインターフェース標準化を担う主要技術パートナーとして参画。
航空局やATC(航空交通管制官)と、民間のドローンオペレーターや空飛ぶクルマの運航者をつなぐ、双方向の情報共有基盤を開発しています。
特筆すべきは、Uniflyが持つ欧州8カ国での国家レベル導入実績。
この経験をもとに、複雑な規制や法体系の中でも柔軟に対応可能なUTM技術を提供しており、空域の安全性と商業活用の両立を現実的に実装できる企業と高く評価されています。
リアルタイム空域調整「DAR」の革新性
ENSUREの中核技術のひとつが、DAR(Dynamic Airspace Reconfiguration:動的空域再構成)です。
これは、ドローンの飛行状況、気象データ、有人機の航路、イベント発生時の緊急対応などを即時に判断し、空域の制限や解放をリアルタイムで自動制御する仕組みです。
これにより、従来なら数時間前に決定されていた飛行計画が、わずか数分単位で動的に変化させられるようになり、ドローン配送や都市内移動において、機動性と安全性が飛躍的に向上します。
また、UniflyはこのDARシステムのUI/UX部分も設計しており、現場のオペレーターが直感的に扱えるインターフェースを提供しています。
これにより、導入障壁を大きく下げ、空域管理の民主化が加速すると言われています。
欧州主要機関との連携と開発体制
ENSUREプロジェクトには、Uniflyの他にAirbusやEUROCONTROL、ENAV、Indraなど、欧州航空業界の中核企業が多数参画しています。
プロジェクトリーダーであるIndra社が統括する開発体制のもと、各国の航空管制当局と民間企業が連携し、一元的かつ柔軟な空域運用の設計が進められています。
2025年5月には、アイスランドのTern Systems社にてオープンデーが開催され、各社の成果発表と今後のロードマップの共有が予定されています。
ここでUniflyが示すUTMの成果は、日本を含む他地域への技術移転に大きく影響するでしょう。
【考察】Terra Droneが主導することで何が変わるのか

日本企業が欧州空域改革に参画する意義
なぜ日本企業のTerra Droneが欧州の次世代空域構築に深く関わっているのか。
その意義は単なるビジネスの越境にとどまりません。
欧州では早くから「U-Space」の法整備と社会受容が進んでおり、2023年には特定地域での実運用が開始されています。
その最前線に、日本発のドローン企業であるTerra Droneが関与しているという事実は、日本の技術力と信頼性が国際基準に達している証ともいえます。
Terra Droneはこれまで、測量やインフラ点検の現場に特化したソリューションを提供してきましたが、今回のUniflyとの連携を通じて、空域そのものの“運用ルール”の設計段階に加わる立場へと進化しています。
ここが他のドローン企業との大きな違いです。
ハードウェアやアプリケーションを提供するだけでなく、ルールづくりの段階から国際社会に貢献するという視点を持てていることが、長期的に見たブランド価値の向上に繋がっています。
また、日本国内ではまだ十分に整っていない
「都市部での高度な空域管理」
という分野において、欧州での経験値は将来的に大きな武器になるでしょう。
特に、都市の上空でドローンが“当たり前に飛ぶ”時代を見据えると、現在のTerra Droneの動きは非常に戦略的です。
ドローン×有人機の共存がもたらす新たなルール形成
現在、世界の航空管理は有人機を前提に設計されています。
しかし、近年のドローン普及により
「無人機と有人機が同時に同じ空を飛ぶ」
という状況が現実のものになっています。
ここで問われるのが
「どうすれば衝突や通信トラブルを避け、安全に共存できるか」
という点です。
ENSUREプロジェクトでは、これまでの航空管制システム(ATM)と、無人航空機の運航管理(UTM)を組み合わせた、新たな統合管理体制の構築が進められています。
そして、その中核にあるのが、リアルタイムで空域を再編成できる「DAR」技術です。
この技術が本格導入されると、一時的な飛行禁止区域の設定、緊急避難ルートの確保、突発的なイベント時の即時対応などが、高度に自動化されるようになります。
これは単に欧州の問題ではなく、日本の都市部や災害現場、イベント空撮でも直結する課題です。
そうした文脈の中で、Terra DroneがUniflyを通じて先行してノウハウを蓄積していることは、国内外の産業界にとって大きな安心材料となるはずです。
つまり、ドローンが日常的に空を飛ぶ社会においては、ハードや操縦スキルだけではなく、「空域ルールの設計思想」が問われる時代に突入しているということです。
Terra Droneはまさにその答えを、欧州の現場で体現し始めていると言えるでしょう。
【比較】他社ドローン企業とTerra Droneの違い
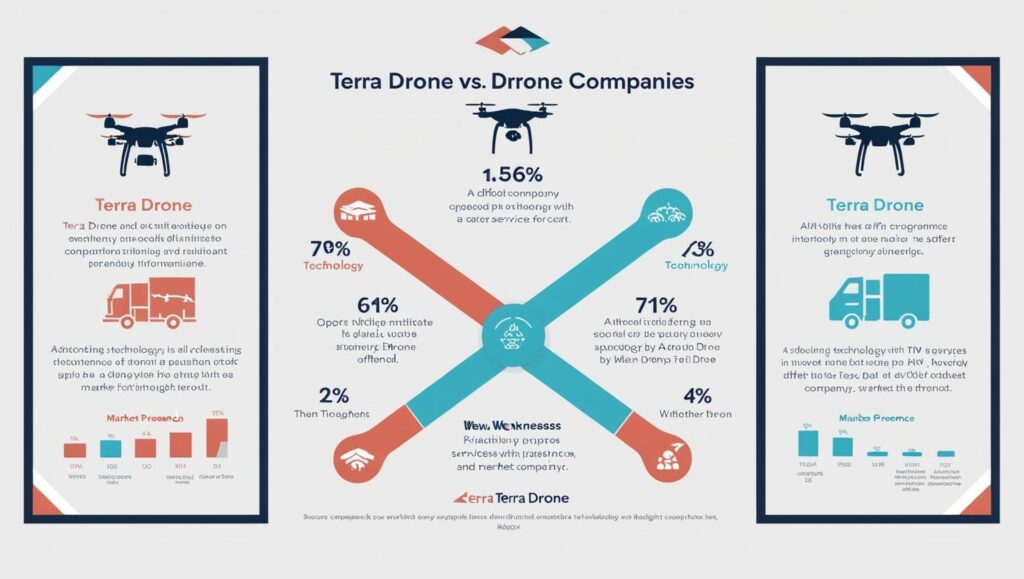
SkyGridやAirMapとの比較
ドローンの空域管理や運航支援という分野において、SkyGridやAirMapといった海外企業は、米国を中心に強い影響力を持ってきました。
両者ともAIを活用したフライトプラン生成や空域マップの自動更新に優れたプラットフォームを展開しており、商用ドローンの運用支援に特化したソリューションを提供しています。
しかし、Terra Droneとの決定的な違いは
「政策レベルの空域構造そのものに参画しているかどうか」
という点です。
SkyGridはNASAやFAAとの連携実績があり、AirMapも米軍や警察とのパートナーシップを強化していますが、それらはあくまで国家機関のプロトコルの中での“システム連携”に近い立場です。
一方で、Terra DroneはUniflyを通じて、EU圏全体の空域ルール形成に直接関与しており、プロジェクトENSUREをはじめとするSESARの複数プロジェクトにおいて、空域の「設計思想」から技術の実装、そして法規との整合性までを一貫して担う役割を持っています。
これは単なる技術提供ではなく、“空をどう運用するか”という根本に対するアプローチであり、他の企業とはスケールも目的も明確に異なっています。
UTM技術の導入実績と信頼性の差
Terra Droneグループが強みとするもう一つのポイントが、UTM(無人航空機運航管理)技術の実装と実績です。
Uniflyは、すでに欧州8カ国で国家レベルのUTMプラットフォームを構築済みであり、各国の航空当局からの正式認証を受けています。
この「制度下での導入実績」は、単なる技術的な優劣を超えた社会的信頼性の証明でもあります。
対してSkyGridやAirMapは、企業単位での導入実績は多数ありますが、「国単位でのシステム統合」や「法制度との連携」においては限定的です。
さらに、UniflyのUTMは、航空管制(ATM)との共通インターフェースを標準化する役割も担っており、リアルタイム空域再構成(DAR)と連動した次世代空域管理の中核として機能しています。
これは、災害時や都市部での即応性・安全性を確保するうえで極めて重要であり、“地図上の飛行可否”を示すだけのUTMとは一線を画す技術水準といえるでしょう。
また、Terra Droneはこのノウハウを活かして、アジア・中東・南米市場へと積極展開しており、グローバルな空域プラットフォーム構築をリードするポジションを築いています。
【国内への影響】日本の空域管理はどう変わるのか
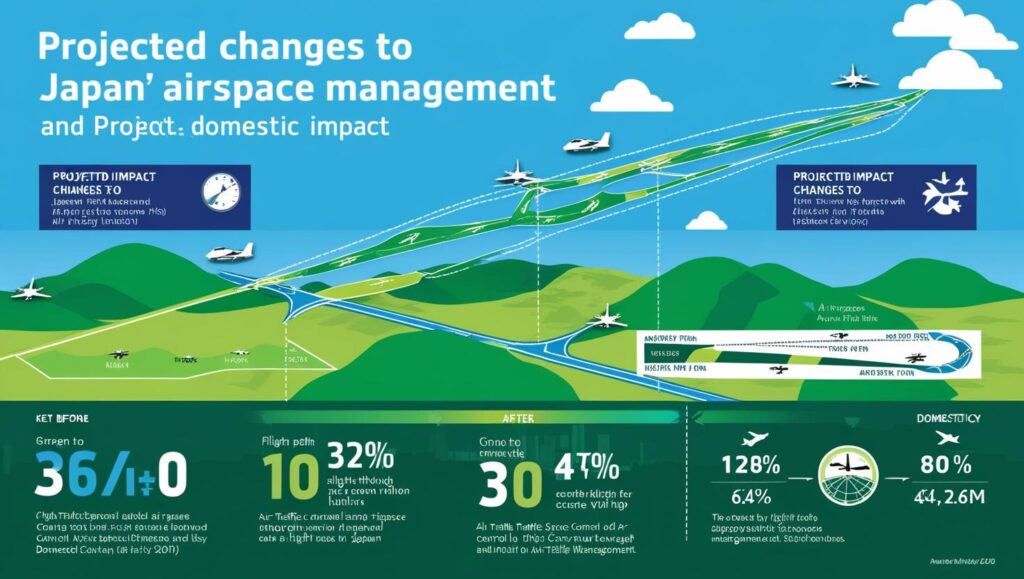
JUIDA資格保有者や事業者への影響
欧州で進行中のU-SpaceとATMの統合が、近い将来、日本のドローン運用環境にどのような変化をもたらすのか──その影響は決して小さくありません。
まず最も直接的な影響を受けるのが、JUIDA認定資格保持者や空撮・点検・物流業務などに従事する商用ドローンオペレーターたちです。
現在の日本では、国交省のガイドラインに従って、飛行計画の提出・承認が求められていますが、その多くは手動の申請・調整プロセスに依存しています。
これが、Terra DroneがUniflyと進めるリアルタイム空域調整(DAR)技術のような動的・自動化された運航管理システムに置き換わる可能性があるのです。
そうなれば、JUIDA講習や既存の操縦スキルに加え、デジタルツールへの理解や、システムと連動した飛行申請・確認能力が求められるようになります。
一見すると「ハードルが上がる」と感じるかもしれませんが、実は現場の負担が大幅に軽減され、作業効率は格段に向上するのです。
特に、災害現場や短時間での空撮依頼といった、即応性が求められる業務においては、この恩恵は計り知れません。
規制緩和とUTM導入のロードマップ
国内では、2022年のレベル4解禁(補助者・目視外飛行)により、有人地帯でのドローンの商用運用が始まりました。
そして、2024年以降も引き続き、法整備と技術導入の両面から段階的な運用拡大が進んでいます。
この背景には、明らかに欧州のU-Space戦略が意識されており、Terra Droneが関わるプロジェクトENSUREの成果が、日本国内の法整備・技術導入にも影響を及ぼす可能性があります。
国交省はすでに、2025年を目処に次世代UTMの国内展開を視野に入れており、公共・民間が協働する標準化の枠組みづくりが進められています。
この際、欧州で実証済みの仕組みは高く評価される傾向があり、UniflyのDARやU-Space統合のノウハウを持つTerra Droneが、そのまま“国内実装パートナー”として抜擢される可能性も充分にあるといえるでしょう。
そして、これはJUIDA資格を持つ事業者にとっても大きなメリットになります。
なぜなら、UTMと連動した高度な飛行管理能力は、将来のドローンライセンス制度や認定講習の中核になっていく可能性があるからです。
つまり今後は、「飛ばすだけ」ではなく、「どう連携し、どう安全に空を共有するか」がライセンスの評価軸となる時代が来ると考えられます。
Terra Droneが国内の空域改革にどう関与するか──それは、ドローン事業者や操縦者自身のキャリア戦略にも直結する、見逃せない変化なのです。
【まとめ】Terra Droneが切り拓く未来の空へ

今後の動向と2025年の注目ポイント
2025年──それは、空の常識が塗り替えられる年になるかもしれません。
Terra DroneとUniflyが参画する欧州の次世代空域プロジェクト「ENSURE」は、単なるドローンの安全飛行にとどまらない“航空インフラ改革”を目的としています。
このプロジェクトの成果として注目されるのが、U-SpaceとATMのリアルタイム統合、そして空域のデジタル再構成=DARの実装です。
これにより、ドローンと有人機が混在する都市部での空域運用が、一気に現実的になります。
5月に予定されているアイスランドでの成果発表イベントも、Terra Droneにとっては“節目”となるタイミングです。
ここでUniflyが示す運航システムの成熟度や統合成果は、日本を含む各国の空域政策にも大きく影響を及ぼす可能性が高いといえるでしょう。
これまで「ハードの技術力」だけでドローン企業を評価してきた時代は終わり、これからは“空域そのものをどう設計し、運用できるか”が本質的な差別化になります。
その点において、Terra Droneは世界でも数少ない「戦略的リーダーシップ」を発揮できるポジションを築いているのです。
ドローン事業者が今、押さえるべき行動とは
この流れを受けて、日本国内のドローン関連事業者が取るべきアクションは明確です。
まず第一に、技術動向を把握し、変化を恐れずにキャッチアップし続ける姿勢が必要です。
Terra Droneが欧州で構築しているU-Space+DARの環境は、いずれ日本にも輸入され、国交省主導のUTM制度に組み込まれる可能性が非常に高い。
つまり、今後の空域管理や飛行申請は、“ポチッとボタンを押すだけ”のようなレベルに自動化される未来が待っているということです。
その未来に備えるには、操縦スキルや機体知識だけでなく、「空域ルールやシステム連携の理解」が欠かせません。
例えばJUIDAライセンスを取得している方や、これから取得を検討している方にとっては、単なる「資格を持っている」という状態から一歩進み、“空域活用のプロフェッショナル”としての知見を磨くタイミングに来ているのです。
さらに、Terra Droneが示すグローバルな展望は、「日本国内だけを相手にする事業モデル」から脱却するヒントでもあります。
アジア、中東、欧州と展開を拡大している彼らの事例から学べることは多く、国内にいながらでも国際標準への適応は可能です。
空はひとつであり、国境を越えるインフラです。
だからこそ、日本のドローン事業者が今押さえておくべき視点は、“グローバルでの標準化・制度化への接続”なのです。
Terra Droneの動きを一過性のニュースとして終わらせるのではなく、次の戦略の起点として捉えることこそが、今後の空域ビジネスで生き残る道になるでしょう。
最新情報はXで発信中!
リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!



