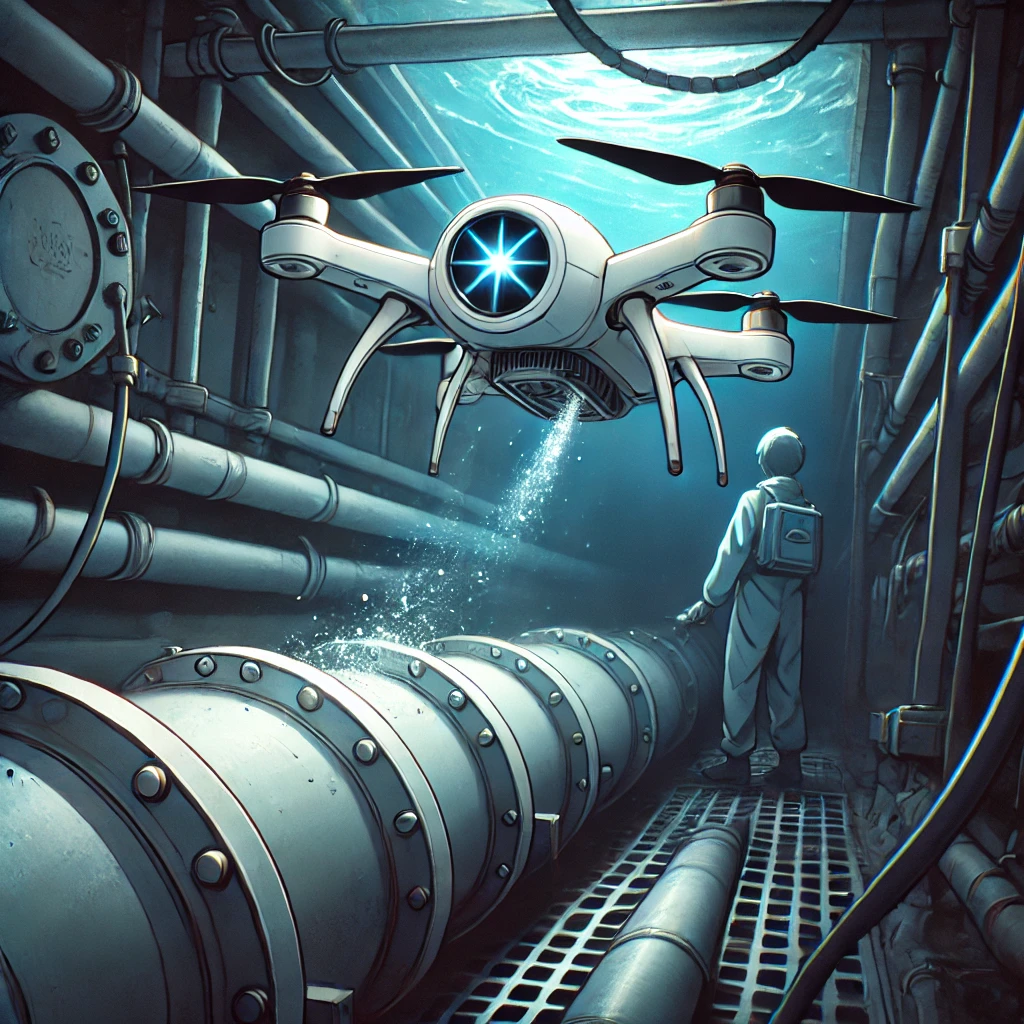ごきげんよう。
「スカイテックラボ」へようこそ。
※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。
「Terra Drone」という名前を耳にしたことはありますか?
この日本発のドローン企業が、なんとサウジアラビアで下水道検査に革命を起こしているのです。CCTVを搭載した水中ドローンを活用し、満水状態の下水管でも検査可能という、従来の常識を覆す取り組みが話題となっています。
そこで今回のテーマは、「その技術、日本の下水道検査でも活かせるのか?」という点。都市インフラの老朽化が進む日本にとって、点検の効率化・省人化は急務です。
この記事では、
- Terra Droneが実施したサウジでの下水道検査の実態
- 日本国内での導入可能性や課題
- 実際にインフラ点検を経験してきた私の視点からの考察
について、詳しく掘り下げていきます。
ドローン=空撮だけと思っていた方には、目からウロコの内容になるはず。「Terra Drone」の今を知れば、未来のインフラ点検の姿が見えてきます。
【JUIDAニュースレター】の最新情報からのものです。
詳細な情報や最新の更新については、JUIDAの公式サイトをご参照ください。
Terra Droneとは?世界で注目される理由
日本発のドローン企業「Terra Drone」の実力
Terra Drone(テラドローン)は、東京都渋谷区に本社を構える日本のスタートアップ企業です。
創業以来、ドローンの設計・製造から運航管理システム(UTM)までを一貫して提供しており、産業用ドローンサービスの世界ランキングで1位を獲得するなど、世界からの注目度は極めて高いです。
国内では測量・インフラ点検・エネルギー分野での活用が進み、自治体や大手ゼネコンとの協業も実績多数。さらに海外展開にも積極的で、アジア、中東、アフリカ、ヨーロッパなど、10ヵ国以上でサービスを提供しています。
ただの空撮ではない、社会課題の解決に直結する技術を持つことが、Terra Droneの真の強みです。
世界ランキング1位を獲得した背景とは?
2024年、業界分析機関「Drone Industry Insights」による調査で、Terra Droneはドローンサービス企業ランキング世界1位に選ばれました。
その背景には「技術力」「安全運航ノウハウ」「国際展開力」という3つの柱があります。
特に注目されたのは、危険・狭所のインフラ点検における自律飛行技術。これにより、従来人が立ち入れなかった空間でも、正確かつ効率的な点検が可能となりました。
また、世界中でのUTM導入実績も評価され、低空域経済圏の構築に貢献しています。
企業規模や資本力では海外大手に劣る部分もありますが、「現場主義」と「解決志向」が、世界に通用する強みとなっているのです。
導入実績と海外での展開
Terra Droneは、国内外で累計3,000件以上の実績を持ち、特に海外市場での展開が加速しています。
アジアではインドネシアやマレーシア、中東ではUAEやサウジアラビアにおいて、インフラ点検・災害監視・プラント管理など、幅広い分野で導入されています。
サウジアラビアにおいても、国家プロジェクトに準じる下水道点検に参加しており、現地の国営水道会社と直接提携する形での実証は、今後の国際入札競争でも大きな武器となるでしょう。
日本発の技術が、グローバルスタンダードになる日も遠くないと確信できます。
サウジアラビアでの下水道検査実証とは

38kmにも及ぶ下水道検査の全貌
サウジアラビアのジェッダ北部において、Terra Droneが実施したのは、全長約38kmに及ぶ下水道管の点検プロジェクトです。
従来の点検方法では排水が必要で、時間も人員も大量に必要となるケースが一般的。
しかし、今回導入されたのは水中型ROV(遠隔操作型無人機)でした。
このROVは、水が満たされた管内でも自在に移動でき、CCTVカメラでリアルタイム映像を取得。
地中レーダーとパイプロケーターを併用することで、正確な位置情報も同時に収集できるため、高精度かつ迅速な診断が実現しました。
特に重要だったのは、都市部の交通インフラを止めずに作業を行えた点です。
道路を掘削せずとも作業が完了する点は、現地行政からも高く評価されました。
CCTV搭載水中ドローンの驚きの機能
検査に使用されたドローンには、高解像度CCTV(監視カメラ)が搭載されており、満水状態でも内部の状態を正確に把握できる設計になっています。
特筆すべきは、最大400mまで到達できるテザーケーブルによって、長距離区間でも安定した通信と映像取得ができるという点。
また、マンホールからの進入によって、点検対象範囲にほぼ無制限でアクセス可能な構造になっており、配管のひび割れ・剥離・異物混入などの微細な異常も可視化されました。
これにより、早期補修・トラブル予防の判断がしやすくなったのです。
現地の課題にTerra Droneがどう対応したか
点検精度の向上
サウジアラビアでは、急速な都市開発によって図面や記録がバラバラなまま放置されていることも多く、マンホールの位置や配管構造が不明なケースが頻出していました。
そこでTerra Droneは、地中レーダーとGPSを連動させた位置特定技術を導入。
このアプローチにより、点検範囲を効率的に絞り込み、的確な補修提案と診断精度の向上を同時に実現したのです。
コスト・作業時間の削減
従来の点検では、大掛かりな排水作業と作業員の交代制勤務が必要でした。
しかし、Terra Droneの技術では、水を抜かずに検査が可能なため、コスト面でも大幅な削減が可能となりました。
この効率化によって、通常3週間以上かかる点検を、実質5日間で完了させたという記録も報告されており、インフラ点検の概念を大きく変える結果となりました。
まさに、「点検の無人化・可視化・高速化」が現実となった瞬間です。
Terra Droneの技術は日本でも使える?
日本の下水道事情と課題
結論から言えば、Terra Droneの水中ドローン技術は、日本の下水道点検においても有効かつ実用的です。
ただし、そこには日本特有の事情や課題が存在します。
日本の下水道網は、戦後から高度経済成長期にかけて急速に整備されました。
その結果、現在では全国におよそ48万km以上の下水管路が敷設されており、これは地球12周分に相当する長さです。
しかし、多くの下水道施設はすでに耐用年数を迎えつつあり、今後ますます老朽化対策が求められます。
一方で、点検作業はマンパワーに依存しており、点検員の高齢化や人手不足が深刻です。
さらに、都市部では交通規制の制約が多く、長時間の作業が難しいといった制約もあります。
こうした状況下で、Terra Droneが実証したような排水不要かつ狭所に対応可能なドローン技術は、まさに日本のニーズに合致しています。
国内導入に向けた3つのポイント
法規制・安全面の整備
日本国内で水中ドローンをインフラ点検に用いるためには、いくつかの法的な整理が必要です。
陸上のドローンとは異なり、水中での使用に明確な基準はまだ整備されていない部分もあります。
とはいえ、国土交通省が定める無人航空機の飛行ルールに準じ、安全性・データ保護・通信管理などの指針をしっかり構築すれば、導入は難しくありません。
特に公共インフラを対象とする場合には、自治体の承認や第三者機関との連携も必要となるため、導入初期のハードルは少々高くなります。
ただし、その分、制度整備が進めば全国へのスピード展開も期待できます。
地方自治体との連携の可能性
点検業務は、全国の市区町村単位で実施されているケースが多いため、地方自治体との連携が鍵となります。
特に、人口減少が進む地方では人手不足が深刻であり、ドローンによる省人化・効率化は切実な課題解決策となります。
すでに一部自治体では、JUIDA(一般社団法人 日本UAS産業振興協議会)認定事業者と連携して、実証実験を行っているケースも出始めています。
この流れが全国的に広がれば、Terra Droneの技術にも大きなチャンスが訪れるでしょう。
狭所・暗所対応の「Terra Xross 1」の活用性
2025年1月に発売された新型点検用ドローン「Terra Xross 1」は、日本市場を強く意識した設計がなされています。
特に注目すべきは、屋内や暗所でも安定して飛行できるセンサー性能です。
これにより、従来の点検員がアクセス困難だった箇所でも、安定的にデータ取得が可能となりました。
狭いマンホール、曲がりくねった配管、湿気や照度の低い空間など、日本の下水インフラに特有の環境に対応できる仕様は、他社製品と比べても大きなアドバンテージといえるでしょう。
現場ニーズに即した機能と価格帯を兼ね備えており、導入障壁も比較的低く、自治体から中小企業まで幅広く対応可能です。
【比較】従来の下水道点検 vs Terra Droneの水中ドローン
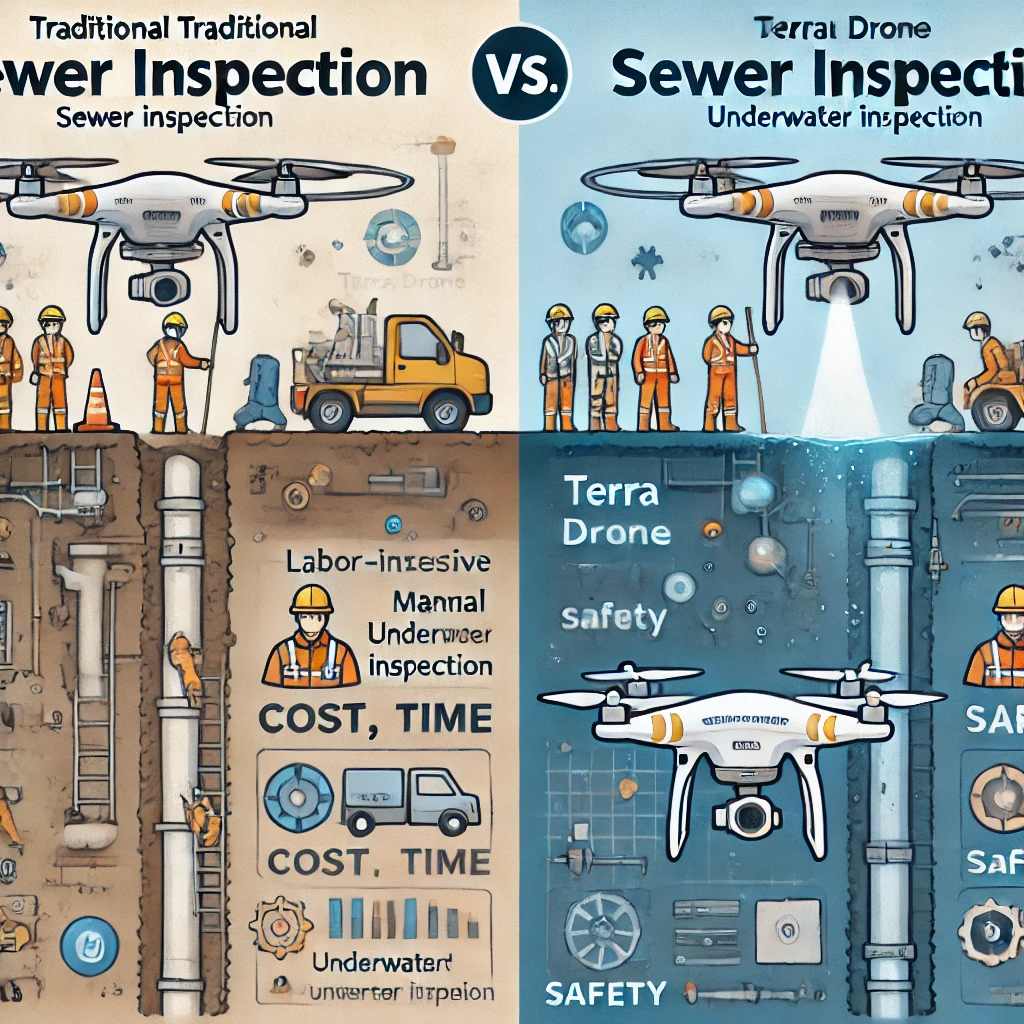
作業工程とコスト面の違い
従来の下水道点検では、管内の水をすべて抜いた上で、人が直接進入して目視で確認する手法が一般的でした。
この方法では、排水処理に数日〜数週間を要し、その間は交通規制や安全管理にも膨大なコストがかかります。
一方、Terra Droneの水中ドローンは排水不要・遠隔操作・リアルタイム映像取得が可能なため、作業日数が圧倒的に短縮されます。
これにより、コストは最大で6〜7割削減できる事例も報告されており、定期点検が義務付けられている自治体にとっては非常に大きなメリットとなります。
精度とリアルタイム性の違い
従来の方法では、作業後に撮影した写真やスケッチに基づき報告書が作成されますが、異常の見落としや主観の混入といった問題が残っていました。
これに対して、CCTV搭載ドローンはリアルタイムで内部状況を映像化しながら、異常個所をAI解析と連動させることが可能です。
これにより、誰が見ても納得できる客観性の高い記録が取得でき、修繕計画の信頼性も向上します。
現場の安全性・省人化の観点から
点検作業に従事する人員の安全も、現代のインフラ保守においては無視できない要素です。
従来は、酸欠リスクや崩落の危険といったリスクを伴う中での作業でしたが、ドローンを活用することで、作業員が現場に立ち入る必要がなくなります。
また、遠隔操作や自動航行によって、1名での点検も現実的になっており、作業の省人化はもちろん、女性や高齢者など多様な人材の参入も可能にします。
人材確保が難しい地域では、この「ドローン省人化モデル」が、今後のスタンダードになっていくかもしれません。
Terra Drone技術のインフラ点検への応用可能性
下水道以外での活用シーン
Terra Droneの強みは、下水道点検にとどまらない点にあります。
もともと同社は、測量・プラント点検・鉱山探査・建設現場の3Dマッピングなど、多様な業界でソリューションを展開してきました。
今回のサウジアラビアでの下水道検査実証は、その中でも「インフラ分野での新しい応用の一例」にすぎません。
たとえば、トンネル内部の亀裂検知や、貯水池の水中構造物の点検、さらには発電所やダムの底部構造の点検など、水中・狭所・高所という人間が近づきにくい場所での活躍が期待されています。
特にこれからは、災害時に迅速な状況把握が求められるケースも増えるため、ドローンによる自動巡回システムや、AI分析を組み込んだ予兆検知システムとの連携も視野に入ります。
住宅設備や狭所点検などBtoB市場での展開
日本国内では、住宅の老朽化に伴い、設備配管や空調ダクトの劣化も問題となっています。
しかし、現状はこうした住宅設備の点検には、天井裏や床下といった極めて狭い空間に人が入り込む必要があり、作業者の身体的負担や安全性リスクが常に付きまといます。
ここで注目されているのが、Terra Droneが開発した屋内点検用の小型ドローン「Terra Xross 1」です。
わずか数十センチのサイズで、暗所・狭所でも安定飛行が可能。搭載カメラの映像はリアルタイムで確認できるため、住宅設備会社やビルメンテナンス業界など、BtoB市場での展開が見込まれています。
この流れは、IoTやスマートホーム技術と組み合わせることで、将来的には「点検の自動化・常時監視」へとつながっていくでしょう。
つまり、Terra Droneの技術は、単なる一時的な便利ツールではなく、社会の維持管理コストそのものを変革する鍵になり得るのです。
建設・インフラ系企業との提携のチャンス
現在、建設業界では慢性的な人手不足と高齢化が進み、「技術継承」「現場力の維持」が大きな課題となっています。
そこに、Terra Droneのような自律飛行・高精度センシング技術が導入されれば、若手技術者の負担軽減や、省人化による効率改善が期待できます。
特にゼネコンやインフラ保守大手との連携は、大規模な橋梁・トンネル・空港設備などにおける点検業務での導入を後押しします。
実際、海外ではすでに複数のグローバル建設企業と提携が進んでおり、日本市場でも今後同様の展開が予想されます。
このような企業提携により、技術導入が加速し、最終的には自治体や一般消費者にも恩恵が届く「点検革命」が訪れることでしょう。
スカイテックマスターKの考察~日本は何を学ぶべきか~
ドローン技術がインフラを救う未来とは
私自身、これまで空撮から測量、インフラ点検まで様々な現場でドローンを活用してきましたが、やはり一番感じるのは「ドローンは人の仕事を奪うものではない」という事実です。
むしろ、人間の手が届かない領域に入り込み、補完し、助ける存在であると確信しています。
Terra Droneが示した下水道点検の新しい形は、従来の常識を変えるだけでなく、「ドローン=空撮用」という固定概念から私たちを解放してくれました。
将来的には、自動飛行による巡回点検、AIとの連携による予兆検知、そしてロボティクスとの融合により、人間とドローンが共存する新たな社会インフラモデルが生まれると考えています。
日本の導入で期待できる社会的インパクト
特に注目すべきは、地方自治体や中小インフラ企業への波及効果です。
これまで「人手が足りない」「予算が限られている」として点検が後回しにされていた現場に、ドローンという選択肢が加わることで、コスト削減・効率化・安全性の確保が同時に実現します。
また、都市部においても、夜間や早朝など交通量の少ない時間帯に点検を実施できることで、住民への影響を最小限に抑えつつ、インフラの安全を守ることが可能になります。
これは、単に業務効率の話ではなく、「暮らしの質」や「安心感」にまで影響を与える重要な取り組みだと考えています。
道路陥没事故へ活かして
ここ数年、日本各地で道路陥没事故が相次いでいます。
老朽化が進む下水道管の破損や空洞化が主な原因とされており、その予防には定期的かつ正確な内部点検が不可欠です。
しかし、排水や掘削を前提とした点検手法では、時間とコストがかかり、迅速な対応が難しいのが現実。
こうした場面で、Terra Droneの水中ドローン技術は極めて有効です。
満水状態でも管内を自由に移動し、映像とセンサーで空洞・劣化・ひび割れなどを高精度に検知できます。
今後、全国の自治体がこのような技術を積極的に採用していくことで、「事故を未然に防ぐ点検体制」が構築され、市民の命と財産を守る大きな一歩になると確信しています。
まとめ~Terra Droneの未来と日本での可能性~

今後の動向に注目すべき理由
Terra Droneは、単なるドローンメーカーではなく、社会インフラの維持管理という極めて現実的な課題に対して、テクノロジーの力で持続可能なソリューションを提供する企業です。
今回サウジアラビアで実証された下水道点検の技術は、その可能性の“入り口”にすぎません。
今後、自律飛行とAI解析技術のさらなる融合によって、ドローンは「点検する機械」から「未来を予測するインフラパートナー」へと進化するでしょう。
すでにTerra Droneは、航空交通管理システム(UTM)や空飛ぶクルマの運航支援といった“空の次元”にも挑んでおり、その挑戦は単なる企業活動の域を超え、新しい経済圏の創出へとつながっています。
世界ランキング1位という実績に甘んじることなく、次なるフェーズとして「都市インフラの無人化」「インフラ点検のスマート化」を実現するため、国内外での連携と事業拡大が続いていくと予想されます。
とくに自治体・建設業界・インフラ管理企業とのパートナーシップを通じて、現場に根ざした技術革新が進んでいくでしょう。
日本市場での期待と導入への一歩
日本の下水道インフラは、全国的に老朽化が進んでいます。
その一方で、地方自治体は予算や人材の確保に悩まされ、点検やメンテナンスを十分に行えないケースも少なくありません。
そこに、Terra Droneが持つ「水中・狭所・暗所」へのアプローチ技術は、極めて実用性の高い選択肢となり得ます。
すでに一部自治体では、試験的にドローンを使ったインフラ点検の導入が始まっていますが、全国的な導入拡大のカギを握るのは「制度整備」と「成功事例の共有」です。
たとえば、Terra Droneが地方自治体と連携し、定期点検のモデルケースを提示することで、導入への心理的・予算的ハードルは大きく下がるでしょう。
また、同社が開発した「Terra Xross 1」は、下水道に限らず建物内の配管・ダクトなど幅広いインフラに対応できるため、中小企業を含む幅広いBtoB市場にもフィットします。
こうした汎用性の高さは、導入後の継続利用やアップグレードにも柔軟に対応できる大きな強みです。
今後の成長を考えたとき、Terra Droneの技術が果たす役割はますます大きくなることは間違いありません。
「人がやらなくていいことを、ドローンがやる」という時代は、もはや未来ではなく「今、ここ」にあるのです。
そして、それを可能にする日本発の企業が世界で活躍し始めていることは、私たちにとっても大きな誇りであり、地域課題を技術で解決できる新たな選択肢になるはずです。
最新情報はXで発信中!
現場のリアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!